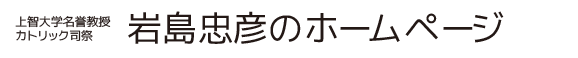信仰と理性
岩島忠彦
「信仰の信憑性は信じることからのみ生じる。不信仰の非信憑性は理性によって必ず立証できる」。筆者が神学生だったときの基礎神学教授P・クナウアーの命題である。信仰を理性的に立証することはできない。しかし信仰に反する命題は必ずどこかに論理の不整合ないし短絡があるので、それはすべて理性で指摘できるという意味である。理性は信仰に対してフィルターのような役割を果たす。すべての信仰に関わらない事がらは理性のフィルターの所で処理されるが、信仰はそのフィルターに引っかからず理性をすり抜ける。
信仰が理性を超える別次元のことであるということは、キリスト教の伝統が常に主張してきたことである。トマスは、信仰を注賦的徳とし、神からの賜物であるとした。彼は、信仰へ至らせる動機は様々にあり得るが、信仰そのものは神のみが与えるものであるとしているのである。ということは、信仰を理性で正当化することは根本的にはできないということである。と同時に、理性的な妨げは取り除くことができるし、そうしなければならないということになる。これが、問題の根本である。
このことは、変わらないが、時代によって様相が異なってきている。古代には、たぶんキリスト教信仰は「知恵」(sapientia)として提示され、他の知恵に勝るものであることを示そうとしたのではないか。例えば、ユスティノスが弁明でロゴス論を提示したとき、中期プラトニズムやストア哲学のロゴス論を適用し、キリストを「ロゴス全体(そのもの)」の自己啓示であるとした。このとき、ユスティノスはキリスト教の教えが、当時のローマ帝国にある様々な哲学(それはしばしばある種宗教的なものとして、市民一般に流布していたのだが)よりもすぐれたものであることを示そうとしたのであろう。
中世は、キリスト教が基本唯一の正しい信仰とされた。そこでは、様々な信仰に対する理性的反省がなされたが、基本理性が信仰に対立することはなかった。そこでは、信仰に対する様々な理解が提示され、やがてはアリストテレス的存在論を用いて大きな体系にまで成長したが、これまた、先行する信仰の理解の試みに過ぎなかった。トマスは、晩年自己の神学的著作を前に、「ワラ屑だ」と述べたという。信仰が大前提とされて、神学はそれを後追い的に理性で検証しようとしたということであろう。だから、中世の標語は、「知解を求める信仰」(fides quaerens intellectum)である。信仰が理性に先立つ。
近世以降、信仰は全く異なった場に置かれた。理性は己が能力の範囲でのみ働くことにしたのである。これによって当然、宗教や神の問題は理性の埒外に置かれた。しかしそこでは、しばしば宗教側からも科学側からも領域侵犯があった。こうした近世以降の歴史を以下辿ってみる。
デカルトとパスカル
R・デカルトは、近世の初頭に理性が信仰に繋がることを示そうとした。彼は、最初から外的なもの、感覚的なものを閉め出し、最も確実なものは、内なる観念であるとした。自分の内なる観念で、自分を超える観念は最終的に神のみであるとした。自分を超える観念が自分の中に存在するのは、そのような存在があるからである。つまり神は存在する。このような論旨を可能としているのは、中世以来の充足根拠率である。新しい装いのもとに論じてはいるが、中世の信仰を前提とした理性の働きから脱していないように思われる。
同時代のB・パスカルは言う。「私は、デカルトをゆるすことができない。彼は、その哲学全体の中で、できれば神なんかはなしで済ませたいと、思ったことであろう。しかし、世界に動きを与えるためには、神に指でひとはじきしてもらわずにはいられなかった。その後では、もう神なんかに用はなかったのだ」(田辺訳『パンセ』角川文庫、77)。所詮、理性から得られるものは本当の神ではない。「神を感じるのは、こころであって、理性ではない。信仰とはそういうものなのだ。理性ではなく、こころに感じられる神」(同278)。これは幾何学的精神を超える繊細の精神の領域である(同4参照)。
人間理性が信仰と区別されるべきであることを明白にした者の一人にI・ニュートンがいる。彼は自然科学の分野で法則性を見出すのに貢献した人物である。その際、その法則性を置いたのは、人を超える存在、すなわち神がその法則性の創始者であるとした。こうして人は世界の法則性を見出すごとに、そのような秩序を置いた神を賛美することになるとした。ここでは、信仰と理性の間に区別がなされている。
理性の真理と事実の真理
やがて流れは、理性と信仰の対決という形へと進んでいく。すでにG・W・ライプニッツは、「理性の真理」と「事実の真理」を区別した。その際、「理性の真理」が「事実の真理」の上部にあるとの認識がある。例えば、「カエサルがルビコン河を渡った」というのは事実の真理である。しかし「カエサル」という主語にあるあらゆる要素を分析すれば、「ルビコン河を渡った」という述語は主語に内包されていると言う。つまり「事実の真理」も「理性の真理」に還元できるということである。ただし「事実の真理」の中に含まれている諸要素すべてを人間が読み取ることは不可能であるというだけのことであり、両者は事実上二つのものとして残る。ライプニッツによれば両者が同一のこととなるのは、「神は存在する」という命題においてだけであるとする。この命題だけは、「事実の真理」でもあり「理性の真理」でもある。
この二つの区別は、ドイツの啓蒙主義者G・E・レッシングにおいて再び現れる。ここでは、「事実の真理」は「歴史の真理」に置き換えられている。「いかなる歴史的真理も論証されえないとすれば、歴史的真理によっては何ものも論証されえないことになる。即ち、偶然的な歴史の真理は、必然的な理性の真理の証明とはなりえない」(レッシング『理性とキリスト教』新地書房、14)。ここで理性は明らかに「必然的理性」として、信仰の対象としての「歴史的真理」と別物とされている。そしてその「必然的理性」とは、何ものも同様に認めざるをえない真理であるとすれば、それは「歴史性」とは別次元の「抽象理性」であるということになる。
「一体何が私にキリストのその他の教えを信じさせるのか。――これらの教えそのもの以外の何ものでもない」(同17)。「キリストとその弟子達が行った奇蹟は足場であって建築ではなかった。足場は建築が終わり次第取り壊される。建築が優秀かどうかを取り壊されてしまった足場だけからでも証明して差し支えないと信じている人は、建築には余り関心を持たない人に違いない」(同49)。先の論理はキリスト教に向けられているのであり、するとキリスト教において大切なのは、キリスト自身よりも彼が説いた真理にあるということになる。レッシングは、「人類の教育」という記事でこれを具体的に示している。「個々の人間において教育に当たるものが、全人類においては啓示である」(同102)。「教育は、人間が自ら内部から手に入れうるものを人間に与える、ただより迅速に、より容易にというだけのことである。従って、啓示も、人間理性が自分の力だけでは到達できないものを与えはしない」(同103)。そうするとキリスト教の真理も、やがてより純粋な「理性の真理」によって乗り越えられる時期に来る。「汝、この初級教科書の最後のページまできて地団駄踏んで興奮している優秀な個人よ、注意せよ、汝より劣等な同級生に、汝が感づいているものを、あるいは既に認識し始めているものを悟られることがないように注意せよ」(同124)。それが今の啓蒙期であるとしているのであろう。
以上のレッシングの立場について、一言だけスキレベークスの言葉で反論しておこう。「歴史的真理」に基づかない真理が人を救った例しがない。人を救う真理は、抽象理性が導き出す万人が正しいと認める真理にはない。例えば、フランス革命における「自由」や「平等」といった標語――それは無規定なモットーであり、結局誰かの救いにはならない。人を救う真理は、人によって仲介されたものだけである。
理神論
さて、啓蒙主義の流れは一貫して理性の優位を説いた。英国がその出発点にあるが、そこから出てくるのが理神論(deism)である。初期の理神論者チャーベリーのハーバートの『真理について』(一六二四年)を例に取ってみよう。彼は自然宗教における基本命題として、次の五つを挙げている。①神の存在、②神を礼拝する義務、③敬虔と徳行の重要性、④改悛することの正しさ、⑤来世における恩恵と堕罪が存在することを信じるべきであることの五つである。それから五十年後にスピノザも『神学政治論』で理神論を説いているが、神の存在と特性、崇拝の必要、博愛と正義の必要性、最終的に人は神によって救われる、悔い改めの必要などを説いており、ハーバートと基本変わらないと見てよいだろう。とは言え、理神論は理性の基準に従った宗教であり、聖書も教会も自らのあり方をそれに従って糺すべきであるとの立場を取る。
やがてJ・ロックやJ・トーランドなどにより、宗教の中心は道徳律を守ることにあるといった形で尖鋭化していった。理神論は、英国からフランスの啓蒙主義者へと受け継がれ、やがて市民革命の流れと一体となり、キリスト教に代わる理性の宗教が提示され、パリでは「最高存在者の祭典」が開かれるにいたった(一七九四年)。
理神論はさらにドイツに受け継がれた。その代表者であるレッシングについてはすでに述べた。カントは『単なる理性の限界内での宗教』において、彼なりの理神論を提示した。I・カントは純粋理性と実践理性とを区別した。純粋理性が対象とするものは、この世の事柄である。そこでは、自由、世界、神の三者は実証されない。それらは超越概念であり、他の事がらと同一レベルで論じることのできないものなのである。しかし、実際の人間が生きる中でこれらの理念は「要請」される。つまり実践理性においては、それらがないと現実が成立しないのである。こうした区別に則って、彼の宗教論が展開される。倫理の基礎は「義務ゆえに、義務を行う」ことにある。ここでは、神は不要である。しかし道徳律を守ることは、人を幸福になるにふさわしい存在とする。しかるに人を幸福にするものは、神以外にありえない。かくして人は道徳律の遵守を通して、宇宙の統括者である神を認めるに至る。それでは、神に対する正しい崇敬とは何か。カントは言う――道徳的生き方から切り離された教会における信心の業は、宗教的欺瞞であり、偽りの神礼拝である。真の神礼拝は、義務ゆえに、義務を行うこと以外にない。結局カントの宗教論は、完全な循環論であるが、理性の範囲内において宗教の本質を擁護したとも言えよう。いずれにしても、ここでも信仰の射程が理性の射程をはるかに超えるものであることが現れてくる。
理神論は一体何だったのだろう。それは総じてキリスト教の基本的な神信仰を純化した形で示そうとし、神への正しい崇敬、それを実現する正しい倫理的行為といった内容を中心としている。啓蒙主義者は総じてこのように純化された信仰形態がキリスト教よりもすぐれた宗教形態であるとしたようである。しかしそのような信仰は一般の人々の中で大した働きをしなかったように思われる。理神論には取り入れられなかったキリスト論の諸要素――例えば、御子の受肉とかキリストの復活、こうした要素抜きにしてキリスト教は意味を持たないのである。理神論がキリスト教に取って代わることは、結局一度もなかったのである。やがてヘーゲルの宗教論のようなものが出てくる。もはやそこでは必ずしも哲学が絶対的優位に立つとは言われない。彼は言う、絶対宗教としてのキリスト教と観念論哲学は、共に最終的なものであり、共に立ちも倒れもするものであると。表象を伴ったキリスト教は、より純粋な思考である観念論に移行すべきである――これがせいぜいヘーゲルにとっての理性の権威の自己主張であった。
カトリックの古典的基礎神学
十九世紀に入るとカトリック神学は、こうした啓蒙主義や観念論に新スコラ学の啓示論で対抗しようとした。こうした論は主として教義神学各論に先立つ基礎神学の中で示されていった。多くの場合、啓示論に先だって宗教論が立てられる。そこでは宗教が人間にとって必須の次元であるということが示される。そしてこのすべての人に共通の宗教性に最終的に応えるのがイエス・キリストにおける神の啓示であると論じられる。
啓示論は、啓示とは何か、啓示は必要か、啓示は起こったかといった手順を踏む(以下、M.Nicolau et al., Theologia Fundamentalis, Madrid 1955(3)を参照する。十九世紀から二十世紀前半にかけてのカトリックでの基礎神学はおおむねこの書と同様である)。啓示が事実あったかどうかの外的基準として、預言の成就と奇跡が挙げられる。奇跡は通常の自然法則の逸脱であり、それは神からのみ可能であるとされる。次いで、四福音書と使徒言行録の史的信憑性が論じられる。これらの準備の後、事実イエス・キリストにおいて啓示があったことが論じられる。すなわち啓示論から「神よりの使者イエス」に移る。ここでイエスの歴史的存在、イエスのメシア性、神から遣わされた者であること、神の子としての自己証言などが取り扱われる。そしてこれが正しいことがイエスによる預言の成就と奇跡によって証明される。その後、イエスにおいて起こった啓示の真理は教会教導職をもって誤りなく伝えられるとする教会論が続く。
少なくとも百年ほどはカトリック教会の主流であったこのような基礎神学が、今日通用しないことは明白である。自由主義神学から始まり今日も続いている史的イエスの研究からしても、例えば四福音書がすべてイエスが語ったまま、行ったままを報じるなどとは言えない。しかし、ここで注目したいのは、当時の基礎神学の論じ方である。まず形式論が先行する。まず宗教・啓示の人にとっての必要性が一般的に論じられ、そこにイエス・キリストが当てはめられる。つまり、理性の枠組みが信仰の提示よりも先行している。これは正しくない。次に啓示の事実を立証するのは預言の成就と奇跡という外的基準である。「公的啓示の歴史的事実を証明するためには、主観的・内的基準は第一義的でない」(前掲書144)。啓示の事実を立証するに際しては、信仰者の主体的関わりは関係しないとするのである。つまり理性偏重、別の言い方をすれば真理問題が意味問題を抜きにして語られているのである。こうした基礎神学の後に教義学各論が続く。そこでは、聖書の箇所(それはすでにイエスの真正な言葉として証明されている)を随時必要に応じて引用すれば事足りるということになる。
このような基礎神学が無効であることは、論を待たない。啓蒙主義以来の理性一本槍の風潮は、カトリック教会に危機感を与え、これに対抗するため自らも同じ理性の土俵で勝負しようとしたのである。その結果、擬似理性的な論を展開し、一般社会からは相手にされない神学を提供する結果となった。「人々は……『信じる理由』の本質を取り違え、……護教論が啓示の事実をより『科学的に』立証することを望んだ」。こうした「似非科学的な様相は、科学者たちを呆れさせるだけの結果となった」「科学者の陣地で科学者によって不均衡な武器で戦わされていたのである」(『神学ダイジェスト』113号、85-86)。一九三〇年のH・ドゥ・リュバックの言葉である。護教論ないし基礎神学の不備が、当時も変わりなくあったことを示している。
こうしたトマスの神学の復興を標榜した新スコラ学の基礎神学は、決してトマスの深みに達することはできなかった。当時の基礎神学の規範となっていたのは、第一バチカン公会議の教義憲章『デイ・フィリウス』(一八七〇年)である。この文書は、さすがに一般的教科書神学のような乱暴な論じ方をしていない。しかし基本、信仰と理性を二つの異なった認識体系としている。「信仰と理性との間に事実上の矛盾はあり得ない。奥義を啓示し、信仰を与えるのと同じ神が、人間の精神にも理性の光を与えたのである」(DS3017)として、信仰と理性は相互矛盾するわけがないと突き放しているわけである。
内在論
十九世紀後半から二十世紀中頃にかけて、こうした基礎神学に対する反論が起こってきた。M・ブロンデルが『行動』(L'action, 1893)を著し、後の内在論的基礎神学の出発点となった。彼は、この著作を「超自然」に対する哲学的決算と位置づけている。出発点を人間存在に置き、人間を全体として行動存在として規定する。人間は自己の現状を超えることを常に目指しているため、必然的に行動存在として規定される。それは自己否定の連続であると言ってもよい。このことは、感性、知性、自由、人格、交わり、モラル、哲学、宗教など、すべての次元で起こっている。その際、「目標としての人間」(volonté voulue)と「そこに向かう精神のダイナミティとしての人間」(volonté voulante)の両者は決して一致しない。つまり自然的人間は、常に欠如態であるということである。ここにおいて、人は「超自然」に対する肯定・否定の決断の前に立たされる。これを否定することは実践的には可能であるが、それは人間規定を事実より狭めることになる。そのため、「超自然」を肯定する立場だけが正しいということになる。こうして人間は「超自然」に規定されている。しかしこの「超自然」そのものは想定されるだけであり、証明や把握の埒外にある。以上のように、ブロンデルは哲学の枠内に留まりながら、「超自然」の入り口まで思考を導いている。
P・ルセローは『信仰の眼』(Les yeux de la foi, 1910)で、トマスに戻り、理性に「信仰の光」(lumen fidei)が働くとして、理性と恩恵の相互補完を説いた。J・H・ニューマンは、J・ロックやD・ヒュームの経験主義ないし懐疑主義の狭い論理に対して、宗教言語に特有の「別の」アプローチを提唱した(illatve sense)。J・ムールーは、信仰の確実性は、外的な行為よりもそれをなす者のペルソナに依拠しているとする。さまざまで多様な試みで、伝統的護教論ないし基礎神学の形式論を乗り越えようとしたのである。焦点は真理よりも善、存在よりも価値、理性よりも意志へと移っていった。こうした傾向は、総じて客観主義的な教科書神学に対して内在論的基礎神学(場合によって総合的基礎神学)と呼ばれた。二十世紀に入ると、フランス中心の内在論的護教論は、H・シェルを通してドイツへと広がっていく。K・アダム、H・ラング、R・グァルディーニといった名前を挙げることができよう。
プロテスタントの流れ
この頃のプロテスタント神学はどうか。二十世紀最大のプロテスタント神学者は、やはりK・バルトであろう。彼はあらゆる人間からのアプローチ、文化・哲学・宗教からのアプローチを否定して、み言葉の神学を樹立した。当然カトリックの伝統的基礎神学は拒絶される。「神語りたもう」(Deus dixit)。神ご自身がキリストを通して語られた。この言葉は、人間のあらゆる知恵を無とし、本質的でないとする。彼の神学は「危機の神学」とも呼ばれる。神の言葉が地上でのあらゆる人の営みを「裁き」(=危機)の前に立たせるからである。この神の語りかけに応えるのは信仰のみである。人の信仰もまた、厳密に言えば人の業ではなく、神の業である。聖霊が働いて信仰を可能にしているからである。こうした神学は当時の自由主義神学に対抗して生まれたものである。当時の自由主義神学、とくに聖書学は、実証学として理性がとらえうる限りでのイエスを、主として比較宗教の手法を通して追求していた。こうした主流に対して、個々の論点と関わるのではなく、キリストにおいて神が語ったという点から見ない限り、聖書の意味はいっこうに現れないとする。
バルトのみ言葉の神学に同調した者は多い。F・ゴーガルテン、E・ブルンナー、R・ブルトマン、E・トゥルナイゼンなどである。信仰と理性が根本的に次元が違うものであるとする点で彼らはバルトに同意していた。しかしそれぞれは独自の発展を示していく。バルトとブルンナーの自然神学論争は有名である。ブルンナーは『自然と恩寵』(1934)で、人間の側に神の「似姿性」があり、その中心は人の主体性、つまり応答責任性であるとする。そこにおいて神の啓示と人間本性との「結合点」があるとした。これは、従来のカトリックの自然神学とは異なる人格中心の自然啓示の可能性を説いたものである。しかしバルトの彼に対する返答の書は、『否!』(Nein !)という短いタイトルであった。バルトにとって、自然はいかなる形でも恩恵と関係しないのである。
F・ゴーガルテンもやがてバルトよりも先へと進む。F・エーブナーの影響下で、彼は啓示を受け取る前提条件として人間間の「我-汝関係」について語る。それが歴史において神の言葉を受け取る条件であると。R・ブルトマンは聖書学者としては、比較宗教学者としての道を歩み、そこにおいては、実際のイエスに到達することができないという否定的な回答を決定的なものとした。しかし信仰者としての彼は、み言葉と実存との間の解釈学的循環について語る。人間は自らの実存状況の中からみ言葉に問いを立てる。み言葉がそれに対して応える。そこで問いを立てる者はみ言葉により自己の実存を照らされるわけだが、同時にそのようにしてだけみ言葉もその意味を開示する。応えられた実存は新たな自己理解から再び問いを発する。み言葉と各自の実存が、相互に解釈し合うのである。こうしたブルトマンの解釈学には、M・ハイデッガーの哲学が影響している。彼の世界理解と実存理解との循環を、み言葉理解と実存理解に置き換えているのである。
このようにして二十世紀前半のプロテスタント神学は、バルトを出発点としており、バルトの基本姿勢は後の人々にも受け継がれている。つまり、神の啓示は人間的なあらゆる思いを超え、人間的な思いを無に帰するという点である。バルトから離れていった人々もこのような大前提には同意していたものと思う。しかしそれだけではすまない。どこかに啓示と世界との「結合点」が必要である。それが人格を中心としたブルンナーやゴーガルテンの自然神学であり、ブルトマンの実存論的解釈学である。彼らのアプローチは、人格主義から実存主義へと進んでいる。同時期にカトリック神学が辿った道とは異なるものの、客観主義から善の問題、理性よりも意志、そして各自の実存のあり方へと視点をずらせていったカトリック神学と不思議な親和性を示している。
『み言葉を聞く者』
カトリックに戻ろう。ブロンデル以来の流れを完成させたのがK・ラーナーである。ブロンデルの『行動』に当たるのは、ラーナーにとっては『み言葉を聞く者』(Hörer des Wortes, 1941)であろう。彼はここで、啓示があるとしたらどのような条件で生起するのかという問いを立てる。以下、彼の論旨を追う。人間は問いを発する存在である。これに対してすべての存在は、人間の認識に対して開かれている。人間は文字通り「すべて」に対して問いを立てるが、すべてから完全な答えを得ているわけではない。人は神に対しても問いを発する。しかし、無限なる者がこれに答える必然性はない。なぜなら神が必然の世界(=自然)を超える自由な存在だからである。つまり、人は神の啓示に対して常にそれを受け止める用意があるが、神が自身を示すか否かは分からない。このような人間が神の啓示を受け入れる潜在的能力を「従順能力」(potentia oboedientialis)と呼ぶ。
そこで、もし啓示があるとすれば、必然・規則性が支配する自然界ではなく、神の自由と人間の自由における応答が生起する可能性を持つ場である。すなわち、人間が時間軸の中で社会的活動をする場、つまり歴史としてのみ啓示は生起する。
それでは、この世を超える存在がどのようにして歴史内で自己を示しうるのか――この世のしるしをもって、この世を超える自己(超越存在)を示す。するとこの世のすべてを表明しうるものであると同時に、それを否定もできるものとして、「言葉」以外には考えられない。つまり啓示はみ言葉として生起する。
さて、人間は神以外のすべてののものに対して問いを発し、部分的に答えを獲得している。しかしこれらのことをなす根拠は存在そのもの、すなわち無限なる存在である神にある。この神に対して人が根源的な問いを発しているからこそ、個別の事実への答えを獲得しているのである。人間の神への根源的な志向性が前提とされてこそ、個別の世界内における認識が可能となるのである。神への志向性と個別の認識の関係は、それをもって測る「尺度」(das Maß)とそれによって測られる個物との関係と言える。
そこで神自身が語るとき、人は自己の本質を達成するチャンスを得るのである。つまり啓示の言葉を受け入れることだけが人間の本来の姿である。つまり神の啓示があれば、人はそれに聞き従う以外にない。二者択一ではない。ただ、人間の自由の欠如から、現実にはこれ、つまりこの啓示を拒絶する可能性も残る。
以上が『み言葉を聞く者』の要旨である。ここに彼の超越論的神学の基本がすでに語られている。人間は基本超越存在である。神への超越が人間の人格を成り立たせている。この無限なる自己超越があるから、世界内における自己超越と自己回帰に意味が与えられる。すなわち無限なる者への超越の地平(Horizont)があって、この世界に対する真や善がその地平のもとに認識され、それが自己認識をも促す。ここでもハイデッガーの哲学が使われている。彼は「世界内存在」「自己投棄」「現存在」などの言葉で、人間の実存的自己理解と世界内的自己超越との相関性を説いた。ラーナーはこの考えをそのまま取り入れている。ただし、こうした世界内的自己超越は、神への超越を前提としていると付け加えるわけである。このことによってラーナーはもはや哲学の領域を超えて、信仰を前提とする領域で語っている。ラーナーは、「神学は信仰の学問である。神学は信仰において受け取られ、把握された神の啓示の意識的・組織的な説明である」と神学を定義している。彼にとって、神学は信仰を前提としていることが明白である。
現代神学の諸方向
ラーナー以降、神学は多方面に展開している。そこではカトリックとプロテスタントの間に本質的境界線は見られない。W・パネンベルクは歴史神学を提唱した。一般史の枠組みの中で啓示を見直そうとしたのである。つまり、人類史全体の中でイエス・キリストにおいて起こったことの意味を位置づけようとしたのである。彼はそれを「神の間接的自己啓示」と呼んだ。キリストが示したことは、歴史の終末において全人類に起こるべきことの「先取り」であるからである。J・モルトマンは、同じ終末を見据えながら、それにパネンベルクのように形を与えることをせず、むしろ終末が現在に「希望」を与え、キリスト者独自の実存を規定するとした。
J・B・メッツは、現代社会の具体性の中で、キリストの福音の意味するところを追求した。彼にとってこのような思索は、必ず社会の現状に対しても、また教会自体に対しても批判的に働くとした。さまざまな形で展開する解放の神学は、メッツの政治神学の意向を中南米などのコンテキストに置き換えた。そこではキリストの福音が人の解放であるとの強調点を得た。
J・モルトマン、E・ユンゲル、H・U・フォン・バルタザールなどは、神の観点から十字架を語った。ここでは、もはやこの世の知恵と神学とは関連しない。とは言え、ユンゲルのようにそこに人間を生かす奥義があるというように、この世との関連を求めている者もいる。
E・スキレベークスは経験という概念を中心に据えて、今日におけるキリストの救いの意義を求めた。彼は人間経験の十全性という観点から、救いは単なる霊的なものに限られるべきではなく、身体的側面や社会的側面をも含むトータルなものであるべきことを強調した。
このように見ると、ラーナー以降の神学は多岐にわたっている。しかし、全般的に見ると、救いの問題に集中しており、われわれとの関係で福音を理解しようとしている。その結果、現代、社会、歴史的なコンテキストの広がりの中で、神学が営まれていると言えよう。そして彼らは総じて信仰の立場を前提として論じている。ラーナーにはまだ見られる、理性の領域と信仰の領域の接点と相違点がそれほど明確になっているように思えない。
現代という時代
信仰と理性。理性という言葉はその沿革が人によって微妙に異なっているということが分かる。今の時代、われわれは啓蒙期以来、産業革命を経て今日の産業技術社会を生んできた関連で理性という言葉を用いるのが一般的である。このような意味では、理性という言葉はかなり狭い範囲で用いられている。価値観などは理性の判断以外のところに置かれているように思う。しかし実際の生活はより幅の広い「理性的」判断を伴っている。そこには、個人の人生観、価値観、信条、信念といったものが加わっていく。これはたぶん理性の範囲を超えて、人間の信仰へとつながっていく種類のものであろう。
こうした理性の二重の用い方が現代の世界にどのような影響を与えているのだろうか。とくに日本の場合を中心に考えてみよう。現代を過去の時代と比較するのは難しい。過去と比べてとくに倫理的に堕落しているとは簡単に言えないだろう。確かなことは、今日の日本がかなりの相対主義に陥っていることである。サブカルチャーなどと呼ばれ、人によって人生観や価値観の違いが顕著であり、一般的にはそれを許容する風潮がある。それが高じて犯罪、それも家庭内暴力とか親殺し・子殺しといった、誰も認められない犯罪へと進むこともある。
こうした現象は、たぶん理性がいわば「技術的理性」とでも言えるものに狭められ、その他のより人間的な面、倫理的面、そして価値観といったものに、かなりのアノミー状態が支配しているということではないか。信仰は、こういった状態の中で流されるわけにはいかない。またかつてのように世間と無関係に独自の世界に留まるわけにもいかない。第二バチカン公会議は、正にこのような態度をよしとしなかったのである。「教会は……人類とともに歩み、世と同じ地上的なりゆきを経験する。教会は人類社会の魂または酵母として、これらをキリストにおいて刷新して神の家族に変質させる使命をもっている」(『現代世界憲章』40)のである。以下、今筆者が考えている信仰から理性に向けての提言を述べておきたい。世界観、人間観、人生観、歴史観についてである。
一つの提案――世界観、人間観、人生観、歴史観
まず世界観。「初めに、神は天地を創造された」(創世記1・1)。聖書は唯一の神を大前提にしている。神があり、その明確な意志のもとに、人間もこの世の他のものも存在する。神と人と世界――この三者が調和を保っているのが楽園であり、理想の状態である。私はこれを三項関係と呼ぶ。失楽園は、この理想の状態が破れ、人が自分と世界との関係のみで生きている状態を指す。二項関係である。超越の次元の喪失である。キリスト教はこれを原罪と呼ぶ。キリストはこの原罪状態から人を救い出し、もう一度、信仰によってこの世のなりゆきをとおして神に向かうことを可能にされた。それを受け継ぎ、神の民として神の国を広げていくのが教会の使命である(『教会憲章』9参照)。
このことを現代日本に適応してみよう。日本は昔から人と人、人とモノの関わりに他の国に類例を見ないデリカシーを示しており、それは今も健在である。しかし基本的に二項関係に留まっている。超越の次元を欠いているのである。この世を超える事がらについては、いわば思考停止と言えようか。もちろん仏教などにおいてあの世、輪廻転生、極楽浄土などの考えがある。しかし実際にどうかと言えば、そこに決定的判断は下さないということになろう。この世を超えるものは神以外にない。そうでなければ(たとえ天使であろうと)被造物に属する。つまり最終的選択肢は二つしかない。私と世界、そしてその他は何も存在しないとするか――あるいは、それらを超え、しかもそれらの意味を最終的に決定する神がいるかである。第三の可能性はない。しかし、私と世界、それで終わりとすることでは、人は最終的に偶然に生まれ、偶然の中で生き、やがては死んで無となるという人生観となる。このような姿勢は人間にとって余りにも否定的であり、実存的に言えば不条理そのものである。残る可能性は、人も世界も、より大いなる者の意志によって存在し、その結末に至るまで神が責任を取ってくれるという見方だけである。これはすでに信仰の言明である。しかし理性的に見ても、もっとも筋の通った可能性であると言えよう。
次に人間観である。人間には固有の精神能力がある。トマスも言うように、すべての人間的営みは、五感から始まる。それを人は経験として受け止める(経験という言葉は人にだけ用いられる)。人は経験した事がらに対して理性的反省を加え、それを何らかの形で理解する(自分に対して意味づける)。人はその理解が正しいかについて自ら熟慮し、最終的判断に至る。これらは主として理性のプロセスである。物事の真偽あるいは正邪は普遍的で人によって異なるということはない。ある人には真であり、他の人にとっては偽であるということはない。人は判断で留まらない。その判断に合致した決断を取り、決断に沿った行動を取る。こうした一連の人間的営みをとおして、人にとっての実存的諸価値、つまり自由、責任、自主性、誠実、正義、価値などが育まれていく。人の不完全さから、その裏経験として、罪とか誘惑といったものが意識されてくる。
以上のような基本的な人間理解は、ほとんど誰でも肯定せざるを得ない。F・ニーチェは別の基準を立てようとした。その結果、人の根本を権力への意志とし、その目標を超人とした。このような人間観は、決して普遍妥当性を持つと言えないことは明らかであろう。日本の場合どうであろう。ありがちな日本人の態度を幾つか挙げてみよう。マニピュレーションに引っかかる、いわゆる「常識」のレベルで動く、世間体や見栄に縛られる、エゴイズムで動く、多数に着き流される等々。こうした次元は、その人の人格の奥に達していない、表層的次元での人の反応である。その際感じられるのは、人間性ではなくむしろ非人間性である。先に述べた基本的な人間観を身につけるとき、人は初めて先の表層的次元から自由となり、人間らしい人間となり、ウソのない誠実な人間性を育むことになる。
正しい人間観に基づいて、正しい人生観が生じる。理性と意志の正しい用い方に従った人間は、自分の人生を冷静にとらえる力をも生む。まずこの世の生にさまざまな時期があることを知る。少年期、青年期、壮年期、老年期――それぞれの時期が他と区別され、前の時期を前提として、別の時期に入る。人はさらにこの世の命は死によって終焉することを正視する。さらにそれが永遠の命の始まりであることをも理解する。つまり人はこの世の命だけで終わりになるのではなく、その先があることを知る。このような人生観は、死でもって終わる人生観よりも希望に満ちている。さらに、後の世の生は、この世の生と無関係であるはずがない。すると逆にこの世の生が永遠の命の「質」を決定するということになり、人はより一層この世の命と本気で取り組むことになる。
こうした二つの命を生きるという人生観は、今の生における優先順位に影響する。金銭・富・仕事・地位などが絶対ではなく、人との関わりや他者への奉仕が優先される。自分に特有の使命をよりよく弁える。生きていることの深い意味を知り、自分に与えられた特別のカリスマにも気づく。さらに、苦しみや不幸、試練などを乗り越えていく精神的強さが生まれる。信仰を伴う人生観は、この世だけに限定した人生観とかなり異なってくると言えよう。
最後に歴史観。先に、「初めに、神は天地を創造された」という聖書の最初の言葉について言及した。創造信仰である。これに対応するのは終末思想である。「わたしはまた、新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。…… そのとき、わたしは玉座から語りかける大きな声を聞いた。『見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとくぬぐい取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも労苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである』」(黙示録21・1、3-4)。神が始めた歴史は、神が最終的に完成される。神が始められた過程を途中で神が放棄するということは考えられない。これが救済史的歴史観である。
通常私たちは歴史の主体は人間であると考える。しかしそれでは個人の場合と同じで、歴史全体が完成するという保証はどこにもない。結局歴史は糸の切れた凧のようなもの、それだけでは何の未来も保証されない。キリスト教信仰によれば、最後には神がすべてを完成へと導き、「神がすべてにおいてすべてとなられ」る(Ⅰコリント15・28)。救済史的歴史観は通常の歴史理解を否定し、これと対立するものではない。しかし、通常の歴史観だけでは決して語れない、歴史の完成について語るのである。
現代は加速度的変化と将来の不透明さについて、たぶんどの過去の時代よりも不安を抱いている。本当に未来への希望があるのか。救済史的希望を持つことによって、この不安を解消することはできない。にもかかわらず、キリスト教には、創造から終末まで、神の明確な意図とその意思の完成によって支えられているという意識がある。それがキリスト者の根源的オプティミズムを支えている。『教会憲章』は、教会を終末に向かって旅する神の民と規定した。教会はキリストが始めた神の国をこの地上で実現することを使命として神から選ばれた集団であるというのである。このような神の国の幅広い理解と、全人類に神の国を広げるという教会の広大な視野――これは、神が最終的に全歴史に責任を取るという終末的希望によって、初めて支えられているのである。
以上の世界観、人間観、人生観、歴史観は、筆者が目下考え得る、信仰と理性の接点である。これらはつながっている。神を加えた世界観がなければ、理性的な生き方をする人間観も支えを失う。それらに則った人生観も然り。そして永遠の命との関連で見ない限り、この世の命単独では、それ自体の不条理さが際立つのみである。そうした個々人の生を抱えている歴史全体もまた神の大いなる意志に支えられているとせねば、逆に先の人間観も人生観も矛盾を来す。
ここに提示されたものは、長いキリスト教伝統を踏まえたものである。なかんずくM・ブロンデルとK・ラーナーの神学の延長線上にあると考えている。これらは信仰における言明である。しかし理性的観点からしても、ほとんど唯一の意味ある人と世界の見方であると考えている。
最初に筆者の基礎神学の師P・クナウアーの鉄壁の命題を挙げた――「信仰の信憑性は信じることからのみ生じる。不信仰の非信憑性は理性によって必ず立証できる」。信仰の領域と理性の領域は明確な区別を持っている。しかし同時に信仰につながらない理性は自己矛盾に陥る。その意味でクナウアーのテーゼは原則的には正しいが、やや消極的に過ぎるように思われる。信仰と理性には必ず「接合点」がある。初期教会の時代にキリスト教はヘレニズム世界の哲学と神話論との批判的対話を行い、そこにキリスト教的価値観を確立していった。理性が勝り信仰が付随的と見られがちな現代世界において、同様のことが起こってもよいのではないかと思う。