「人の子」の生にならって
岩島忠彦
五月二日は召命祈願日とされている。召命というと通常、司祭や修道者の道への神さまからの招きとして理解されている。筆者も修道司祭なので、まずはそのことを連想する。およそ四十年前、二十才で広島の郊外にあるイエズス会修練院に入った頃のことを思い出す。洗礼を受けたのが高一、卒業する頃には信仰に徹し、神さまに身を捧げて生きようと決心していた。あれから世の中も変わったし、カトリック教会も大きく変化した。今ふりかえってみると、当時自分が思い描いていた司祭像や生活形態と現実の自分のそれとはかなり違っている。しかし神学を教え、教会で司祭として働きする中で、神さまと人々のために自分を使っていただいているという幸せを感じ、やっぱり「召し出し」だなと思う
ここまで歩んできて、司祭として生きていることが一番自分らしいと感じる。別の生き方というのを想像しにくい。だから「これはやはり自分の召命だ」と思うわけである。入会するころ、なぜ他の人もこの道を行かないのだろうと不思議に思った。友人たちは、「人それぞれの道がある」と言ったが、私はそれがよく理解できなかった。もちろん今この歳になればよく分かる。一人ひとりが自分だけの顔を持ち、体の特徴も、性格も、好みも能力もみな異なる。そんな中で、自分に与えられた生をどのように生きるのだろうかということは、他人を真似てみて見つけることができるものではない。
信徒の召命について、次のようなことを読んだことがある。私たちは、教会においてジグゾーパズルの一片のようなものである。全く同じピースというのは一つもない。そしてどのピースが欠けても絵は完成しない。そのように私たちには、他の人と入れ替わることのできない使命がある。不必要な人というのはいない。それに気づけば、自分の存在意義を積極的に受け取り、前向きに自分自身を磨き、生きがいを持って進んでいけると。
この考えは、それ以来、私の信念のようなものになっている。こうした見方からすると、特別な聖職者への召命だけが、召し出しというわけではないということになる。むしろ、個人に与えられた自分の生そのものが、すでに「召し出し」であるということになる。まずは、自分自身をよく知り、誠実に自己と取り組んでいくところに召命の道は始まる。それぞれは自分の長所・欠点や才能とその限界とを感じることであろう。しかし、それこそ言わば自分の天命であると悟れば、肩の力が取れ、自分らしい生き方ができるのだろうと思う。不必要にコンプレックスに陥ったり、落ち込んだりすることも少なくなることだろう。
キリスト者であることも、生そのものの召命の延長にあると言えよう。「人」となられた神の御子に従う者は、まずはキリストと同じように、自分に与えられた環境や条件の中で自分の人間性と真摯に取り組むとき、本当の意味でキリストと同化されていくのだと思う。また、ある者は、そうしたキリスト者としての本物のあり方を求めていくとき、司祭職への道や修道生活という選択を取っていこうとするのだと思う。当人にとっては二者択一的な選択ではなく、まっすぐに延びていく一本の道だということになろう。もちろん自由による決断が求められるのだが、それをも越える自分にとっての必然のようなものを感じもするだろう。召命と呼ばれるゆえんである。
このところ、狭い意味での召し出しの減少ということが深刻である。これにはそれなりの問題点や反省し改めるべき要因がいくつもあるであろう。しかし、まずは「人の子」として生きられたキリストに与るという召命を、各人がしっかり受けとめることが大切である。ありのままの自分をしっかりと受けとめ、その中でいただいたキリスト教信仰の恵みを身をもって生きようとする人たちが増えるとき、芯のある司祭・修道者の召命もまた健全な形で育っていくのではなかろうか。
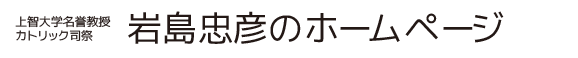

 「今、四旬節の悔い改めとは」
「今、四旬節の悔い改めとは」