聖なる普遍の教会を信じます
岩島忠彦
ローマ要理書と日本の要理書
先日、山口・島根地区の司祭研修会の席上、ある神父様がこんなことをおっしゃいました。「新しい要理書で信者さんたちと研究会をしていると、カトリック新聞で日本の要理書が出ると読み、信者さんたちがどっちを読めばいいのかと言い出して、研究会をやめてしまいました」と。日本の要理書『カトリック教会の教え』は、この原稿を書いている現在はまだ出版されていませんが、お読みの方々はたぶん手にしておられることでしょう。実際、一年もたたない間に、題名もほとんど変わらない数百ページの二冊の要理書を前にすればため息も出るというものでしょう。
このたび『カトリック教会のカテキズム』(ローマの方)に沿って、教理の「教会」の部分について書くようにと言われ、その部分を注意深く読んでみました。そして感じたこと。「さすがローマ」といったところでしょうか。第二ヴァティカン公会議諸文書、とくに教会憲章をはじめ、新教会法の要所要所を引用し、それにふさわしい教父たちの言葉などが引かれ、教会に関して教えられてきたさまざまな事柄(本質・組織・目的など)について細大もらさず総合的に提示されており、大いに刺激を受けました。この点日本の要理書の方は一歩も二歩も劣るかなと思います。二千年の歴史を通して積み重ねられてきた「信仰の遺産」が見事に総括されています。
他方、読みながらずっと続く感覚は、どこかガラスを隔てて触ろうとするようなもどかしさでした。一例を挙げましょう。「キリスト者にとって、『仕えることは支配することです』」(786)。何でこんな苦しい説明をしなければならないのでしょうか。昔から、聖職者は、キリストの三職(祭司職・預言職・王職)にあずかるとされていたのですが、公会議以来、これは本来、神の民、つまり教会全体にあてはまるものであることが強調され始めました。そこで神の民の王職(=支配する務め)を説明するに当たって、右のような文章になるのです。もう一つの例。「信徒」の項目では教会憲章に従って、信徒の特質が「現世的なことがら」(899)に携わることにあるとしているのですが、同じ項目で、「信者は、『……たとえそれが現世的なことがらに関するものであっても、神の支配から除外することはできないのです』」(912、筆者傍点)としています。積極的評価の「現世的ことがら」が、ここでは若干消極的な表現になっています。このズレの説明は簡単です。この引用が、聖職者の務めに信徒も参与するという意向で「カトリック・アクション」が推奨された頃のピウス十二世の言葉だからです。教会憲章の精神とは時代が違うということです。
言いたいのは次のことです。述べられている一つひとつは大切なことなのですが、あまり総花的に述べるので、けっきょく何を言おうとしているかが、かえってはっきりしてこない。そしてこれは歴史的背景などを説明しないでさまざまな「教え」を(しかもかなり断定的に)列挙していることに由来すると思われます。実は筆者は日本の要理書の教理の部分を執筆しましたが、「教会」の説明もずいぶん違ったものになりました。筆者の場合、聖書を中心に教会の本質を語って、その誕生以来第二ヴァティカン公会議に至るまでどのような時期を経て今日に至っているかを中心に説明しました。キリスト教文化圏では前提とされている言葉や考え方の背景を説明し、それらの前提がない人も読んで考えれば分かるように書いたつもりです。「たくさんのデータならローマの要理書、信仰内容を理解するためなら日本の要理書」。二つの要理書の区別について訊かれるとき、こう答えることにしています。
進化する教会
さて、本題の教会に話を移しましょう。もうすでに二十年近く前でしょうか、日本の司教総会で公会議後の教会についてお話をさせていただきましたが、そのとき、現在の教会は過去の時代と全く新しい時代との狭間に入っている「過渡期の教会」であると言うことを何度も強調しました。そのとき、ある司教様は、「過渡期なんて歴史はいつでも過渡期ではないですか」とおっしゃいました。しかし今日歴史そのものが、過去のどの時代とも全く異なった時代(キャッチフレーズで言えばポストモダン)に突入している現在、教会の歴史も全く新しい次元に足を踏み入れたのだと、私は思います。一人の人間が誕生して、幼年期・青少年期・壮年期・老年期と自分の過去を前提としながらも、全く新しい人生の時を迎えるのと同じで、教会も誕生したままで留まることはなく、新たな自己の歴史を刻んでいきます。K・ラーナーによれば、教会の決定的な時期を三つに分ければ、ユダヤ教に留まった教会、西欧文明と結びついた教会、世界の教会の時期に区分でき、第二ヴァティカン公会議がこの第三の時期の開始を促したのだとします。
では、この新しい時期の第一の特徴は何でしょうか。私は「グローバリズム」という言葉をあげたいと思います。世界大での人・モノ・情報の速やかな交流は、かつてなかった実質を伴って、人類を一つのものとして意識させる時代に突入しています。これまではお互いに遠かった文化や民族のことがらを、自分の関心事とせざるを得ない時代に入っています。こんな世界にあって、教会のあり方とその具体的使命も、そしてそのための形態も、それまでの教会が経験しなかったようなものとして考えられていかなければならないでしょう。
最近、キリスト教放送局(FEBC)で教会についての話を毎月しています。責任者の方が、第一回目は公会議を中心にして、現代教会の独自性について話して欲しいとおっしゃったので、初回は「進化する教会」というタイトルでお話ししました。いつまでも「過渡期」でもないでしょうから。
全人類の救いの秘跡
第二ヴァティカン公会議、とくに教会憲章は、こうした時代意識のもとに教会について教えを述べています。今、この憲章が示す現代的教会理解の二三のテーマを取り上げてみましょう。ローマ要理書も同じラインで語っています。
まず冒頭、導入の部分で教会憲章は、教会を「秘跡」として提示し、その意味を、「神との親密な交わりと全人類一致のしるしであり道具である」と説明しています。これは、福音の二重の掟(神への愛・隣人への愛)の現代的状況における表現と見てもいいかもしれません。とにかく、この二つのことがらの指摘は、公会議に特徴的なものです。まず、神との親密な交わり。公会議諸文書は、人間の目的は神の命への参与にあるという一貫した出発点を示しています(教会憲章2項、啓示憲章2項、現代世界憲章19項など)。物質文明ともIT革命とも言われる時代にあって、人間の生きる座標の縦軸が不明瞭になっている。そのため世界全体が混迷の度を深めている。そうした状況判断の中で、キリスト者のみならず、すべからく人間は神さまとの交わりにおいてこの世に生を受けてきた目的を達成するというラインをはっきりと打ち出しています。第二の点、全人類の一致も、変わらない隣人愛の命令が、グローバルなレベルで受け止められていると言えるでしょう。つまり、「全人類の救いの秘跡としての教会」は、内向きになりがちだった教会の存在意義と目的を、世界全体の中において新たに確認したと言えるでしょう。
秘義・神の民としての教会
「秘義」(ミステリウム)は、神さま(とその恵み)と直結することがらに使われます。教会憲章第一章は、三位一体の神の救いのご計画の中に教会を位置づけて、教会の本質を秘義として語ります。第一章では父なる神の世界創造のみ業から説き起こし、御子・聖霊の派遣へと進めながら、教会の誕生について叙述しています。また「旅する教会の終末的性格」というキャッチフレーズを冠した第七章では、教会は歴史が続く限りこの地上での役割を果たす責務があること、そして教会は、終末つまり歴史の終わりにはじめて完成するのだということを浮き彫りにしています。こうして教会の存在意義が創造から終末に至るまで、歴史全体という最も広い視野の中に位置づけられています。ここまで見通しをつけて教会を示したのは、やはりこの公会議が初めてなのではないでしょうか。一般史そのものが救済史として示されています。
こうした位置づけの中で、きわめて現実的・歴史的な言葉「神の民」が教会に当てはめられます(第二章)。新約聖書では中心的教会理解だったこの言葉は、これまでなおざりにされがちでしたが、公会議で久々に復活した感があります。新約聖書の時代に教会はイスラエルへ約束された神さまの救いをもたらす務めを自らが帯びていると考え、自分を神の民と理解しました。教会憲章は、現代という時代にあってすべての人に神さまのいのちと恵みをもたらす使命を深く意識して、神の民という自己理解を再提示したと言えます。現代世界憲章は、教会の務めを、「全人類とともに歩み、世と同じ地上的なりゆきを経験する。教会は人類社会の魂または酵母として存在し、それをキリストにおいて刷新して神の家族に変質させる使命をもっている」(40項)としています。
教会の構造と聖性への召命
教会憲章は、右に述べた教会の本質を確認した後、その成員としての「聖職位階制度、特に司教職」「信徒」について第三、第四章で取りあげます。第三章にはエキュメニズムとも関係する微妙な教理的問題が数多く盛り込まれています。教皇制度や教導職の問題などには、まだオープンで神学的解明を必要とすることがらがあります。第四章で信徒が積極的に扱われたことも特筆すべきことでしょう。
こうした基本的教会成員の構造を示した後、憲章はもう一度、教会が全体として「聖性」に召されていること(第五章)、その典型的形態としての「修道者」について(第六章)取り扱います。聖なる教会とスタティックに開き直るのではなく、すべてのキリスト者が聖なる者になっていくようにとの課題として「聖性」が提示されているのです。実際、公会議後、すべての修道会には自己の会憲を見直し、刷新を行うようにとの課題が与えられ、今日それが完了しています。一九九四年には、修道生活に関するシノドスが開かれ、より広いコンテキストの中で「奉献生活」という見方が強調されるに至りました。
このように見ると、公会議は、教会の外的構造よりも内的構造、つまり信仰のあり方そのものが今の時代にあって刷新されることに関心を示しているように思われます。
インカルチュレーション?
これまで述べてきたことのまとめをしておきましょう。教会憲章の教会理解の新しさは、その視野の広さにあります。これまでのどの時代も今ほどに情報や実際の交流によって結ばれたことはありませんでした。教会憲章はこのような時代にあって、教会を全歴史、全世界の広がりにおいて、その存在意義を、しかも三位一体の神の救いと恵みという視点から明確に提示しているということでしょう。
公会議が示したことは、ヴィジョンであり、課題であります。公会議が終わってから四十年足らず。私たちはその課題と様々な形で取り組んできました。「開かれた教会」「信徒中心の教会」「福音宣教」(正確には「福音化」)といったスローガンが立てられました。「教え」よりも「実践」「あかし」が強調されてきました。刷新に向かうとき、必然的に生じる混乱の中で、強い保守主義の主張が現れました。とにかく、公会議が提示した教会の自己理解を実践に移すとなると、けっきょく誠実で地道な努力と愛の実践が必要なのです。私たちがやるべきことはまだまだいくらでもあります。それは、ヴィジョンやスローガンを叫ぶことによって進捗するようなものではないということを徐々に学んできたと思います。
最後に、このシリーズ「カトリック教会の教理と日本人」との関係について。福音が根付くことにおいて二つの面が大切だと常々思っています。それぞれの民族的文化や伝統への土着、そして現代という時代の現実と信仰理解のすりあわせ。日本人という観点からしても、日本的文化伝統よりも現代という要因が今の日本人の精神構造を第一義的に決定していると言えないでしょうか。教会の現代化、そこに「日本の教会」が根づく主要な鍵があるような気がします。
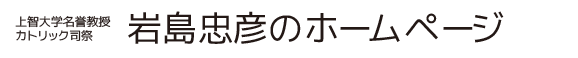

 二十一世紀への橋渡しをした教皇
二十一世紀への橋渡しをした教皇