カトリックの教理を見直す
岩島忠彦
総括?
今年一月から連載した本シリーズも最終回となりました。毎回、個々の教理を扱ってきたので、最後にそれらを見直してまとめてみたいと思います。カトリックの教理は、長い教会の伝統の中で、荘厳な殿堂のように築き上げられてきました。そこには私たちが信仰の基準とし、よすがとするにたる総合性と明確さがあります。ただし、「今」という時代、そして「日本」に生きる私たちカトリック信徒にとって、その意義をもう一度自分たちの視点から受け直す必要があります。こんな観点からこの「まとめ」を試みてみます。
人間とは何か?
この問いから教理は始まります。人間存在の不思議、人生への問い、私は一体何のために生きているのだろうか。教理もまた、こうした「私」の発する問いに出発点がなければ意味がありません。教会は、神とのいのちの交わり、これを人間の目的として教えてきました。ある神学者は、これを人間の「究極的関心」という言葉で表しています。考えてみればこの世に生きていても、この世そのものの中には自分の最終的目的とするものをそこに見出すことはできないものです。
そこで、神を求める人間の心、つまり「宗教心」は人間にとって根元的なものであり、さらに、人は何らかの「宗教」を持つということが必要であると教えられています。確かに今の日本のように、あやしげな宗教が横行している時代には、むしろ無宗教の方が「まとも」などとも思えますが、よくよくつきつめれば、古典的宗教あるいは新興宗教が求めている積極的なことがらは、人間共通の深い思いを示していると言えるでしょう。
啓示と伝承
神を求めるという人間の目的。それは人が自分の生と誠実に向き合うということを通して達成できることですが、最終的には神ご自身がイエス・キリストを通して示して下さいました。これを通常「啓示」と呼びます。啓示というと何かご託宣のような印象も与えますが、神さまが自ら、ご自分の命を通わせ、私たちと交わりを開いて下さったということです。交わりを持てば、その方がどのような方であるかを「知る」ことにもなります。ですからヨハネなどはこの出来事を「恵みとまこと」という二つの言葉で表しています。
それがイエス・キリストによってなされた。このことは、キリストがただの偉人・宗教の創始者であるに留まらず、神から一回限りの使命を帯びて遣わされた方であるということをも意味します。それゆえ、キリストは「神の子」と呼ばれ、また「人類の救い主」「唯一の(神と人との)仲介者」などとも呼ばれるのです。啓示をこのように理解すると、神ご自身が人の歴史全体に対してキリストを頂点とする救いのご計画を持っておられるということになります。そこで信仰においては人類の歴史を「救いの歴史」(救済史)としてとらえます。そこでは、旧約の歴史は特別の啓示的意味を持ちます。また、キリスト後の教会の歴史もキリストにおいて生起した啓示を、いわば「世の終わりまで」伝達する役割を果たすものとしての特別の意味を持ちます。
教会の啓示伝達の業を、総じて「伝承」と言います。伝承の中で最も大切なのは聖書でしょう。旧約・新約併せて、信仰の基準となる神のみ言葉とされます。さらに教導職による教義、礼拝や秘跡、信仰生活を通しての恵みの業の伝達もまた伝承です。キリスト者となる者は、こうした教会の伝承の交わりに取り入れられて、キリストの福音、キリストの救いに与る者となっていくのです。
伝えられた信仰内容の主なことがらは、使徒信条とか二ケア・コンスタンチノープル信条といった「信仰宣言」(信条)にまとめられています。以下、個々の信仰箇条に触れてみましょう。
創造と原罪
創造主への信仰。これは、天地・人類発生の自然科学的描写ではないとすれば、人もこの世も神さまのご意志によって存在し、良きものと肯定されているということへの信頼であると言っていいでしょう。すでに述べたように歴史全体も神の手の内にあり、神によって完成していただけるのだという楽観も、この信仰に含まれていると言えるでしょう。この意味で、天地の創造主、全能の神を信じるということは、神の存在を信じるということと大きくは異ならないと思えます。人間とこの世界がさらに大きな慈しみの神によって見守られているということですから。人間の側から見れば、自分が最後の砦ではないということで、それが被造物としての自己理解です。
そこで、神・世界・人間の本来あるべき関係が楽園として語られており、原罪とその人類全体への広がりは、アダムのとき、つまり人間の歴史の始めから、人はいつもこのあるべき状態にあったためしがないということを教えています。それが罪と呼ばれるのは、人が神との親しい交わりを持てないのは、神ご自身のせいではなく、ひとえに人間の側が積み重ね、作り上げていった状態であるということをはっきりさせるためです。キリストの福音は、本来の人の幸せへと招く、神さまからの新たな働きかけです。ですから、キリストは「救い主」と呼ばれるのです。
イエス・キリスト
イエスは、「神の国」の福音を告げ知らせました。すべての人に神のみ旨がいきわたる時が始まったと宣言したのです。どのように?神さまが私たち一人ひとりを心底大切にしておられることを告げることによって。それは無条件の愛であって、それを示すのが、神のゆるしです。人は自分がゆるされているということを確信しない限り、無心に神に近づくことができないものです。この和解の福音を受け入れ、自分のものとする人は、自分も隣人を愛し、ゆるす生き方を始めます。すると、そこまで神の国は到来することになります。イエスの教えとは、そんなものでした。
イエスは単に教えただけではありません。自らが神の愛とゆるしを体現して、生き、かつ死なれました。人はそれが告げられるだけでなく、それを直に受けることができたということです。イエスの業に接することによって、人は癒されました。「み力」とも呼ばれる神の命が働いて、その人をいわば再生させたからです。イエスが与えたこの命は、通常「聖霊」と呼ばれます。この癒しは、聖書が述べる奇跡に限られることはなく、信仰によって福音を受け入れるすべての人が根から癒されていったということです。それが失楽園以来の「救い」です。より肯定的に言えば、神の命(聖霊)によってついに神の子とされる恵みです。イエスは、このように福音を実際に実現しつつ、福音を告げたのでした。
イエスは、その受難と死をもって神の愛の究極的あかしをなし、その復活によって福音の正しさを示し、さらに神の愛を絶えず取り次いで下さる「生ける方」となられました。そのとき以来、イエスは、彼に従う者の中で「メシア」(キリスト)、「主」、「神の子」、「人の子」と呼ばれるようになったのです。
三位一体の神
キリスト以降の教会は公会議などを通して、要所要所で教義を制定してきました。まずは、キリストについて。ニケア公会議では、彼が本質的に神に属する方であることを、カルケドン公会議では、「まことの人、まことの神」であるということを。このことは、ちょっと分かりにくいことかも知れませんが、もしキリストが偉大ではあるが、一人の人間に過ぎないと考えるなら、彼の福音は、真に神から人間に対して発せられたみ言葉でなくなります。この教義はキリスト教信仰の土台にかかわるものだったのです。次に、神の愛と命の霊、聖霊の神性が宣言されました。これまた、それが被造物であるなら、もたらされた命は、神の命、神の救いではなくなってしまうからです。このようにしてユダヤ教やギリシア哲学のあらゆる反論にもかかわらず、父と子と聖霊、三位一体の神の教義が示されたのです。これは、決して後で思弁が作り出した教えではなく、新約聖書の信仰をつきつめて考察し明確にしていったもので、キリスト教信仰の生命線に関わる教理です。
これらの教義は、古代に確認されたものですが、さらに古代、中世、近世を通して、聖霊の人間への働きのありようを扱う恩恵論、その恵みが与えられる中心的場である秘跡についての教えなどが順次確認されていきました。
教会
このような教理は、福音を受け継ぐ教会が定めてきたものですが、その教会そのものは、ずっと「キリストの体」と呼ばれてきました。それだけ教会は、復活したキリストと結ばれ、彼と一体となっているということです。教会はまた「聖霊の神殿」とも呼ばれています。使徒言行録は、聖霊が教会を成立させ、さらに存立を支えているのだということを強調しています。教会は、新しい「神の民」とも言われているわけで、教会が本質的に父と子と聖霊の神の交わりの中にあり、その生命の現存によって、生きた共同体として今日まで福音を示し続けてきたということが分かります。
教会そのものが教理の対象となったのは、十四世紀以降、特に宗教改革を契機とします。教会分裂という新事実に直面して、どれが真正な教会かという議論が高まったからです。カトリックとプロテスタントの教会理解は、それぞれの強調点にズレがあるものの、相互に矛盾するものではないと思います。もう一度、第二ヴァティカン公会議が、「全人類の救いの秘跡」として教会を定義し直しました。グローバルな今の時代において、初めて教会はより広い時間・空間の枠組みの中で、より普遍的な教会の使命をはっきりと自覚したと言えるでしょう。教会は、終末に至るまで、キリストが始められた神の国の完成に力を尽くしていくことでしょう。
終末
死、審判、天国、地獄。これらをカトリックは従来、「四終」として教えてきました。死をもってこの世の生は完結し、審判においてその意義は決定する。その生に応じた形で人は神との交わりに入る。これが天国であり、それは最初に述べた人間の目的の実現です。もし天国の本質が神との完全な一致にあるのなら、神と異質な要素が取り除かれる「練獄」というものがあるということも必然と言えるでしょう。
教会はずっと審判に個人の死に続く「私審判」と、世の終わりの「公審判」とを区別して教えてきました。何で二回も?という思いもしますが、これは自分という人間の意義が定まる二つの側面と、まずは考えるべきではないかと思います。人間は個人として死をもって自分の存在意義が決定します。しかし人は社会的存在であり、善くも悪くも周りの人々との関連において意味づけられます。神の国の完成が全被造物の完成であるのなら、世界全体、歴史全体との関連において、最終的には一人の人の存在意義ははっきりするということになります。これと関係して、「体の復活」という大切な教えがあります。人間は、心と体をもってこの世に生を受けます。自分の体をもって生き、働き、人間関係を結ぶ。ところが、それは今だけのことであって、死後はいわば魂だけで永遠の命を生きるというのはどう見ても不自然です。天国はあくまで人間として生きた自分の生、そして関わった人やことがらすべてが完成を得る場である。それがこの教えが指し示すヴィジョンです。終末についての教えは、これまで個人主義的にとらえられる傾向が強くありましたが、今日、歴史全体・人類全体という広い視野で理解されるようになってきています。
展望
おおざっぱながら教理内容をざっとまとめてみました。こうしてみると、長年にわたって信じられてきた個々の教えは、それほど分かりにくいマニアックなものでもなく、人間の中心的関心とかかわるものであること、全体として今の私たちにも骨太に生きる基盤と希望を与えてくれるものであるということが分かります。
キリストがもたらされたものは、もともと「福音」、つまり喜ばしい知らせと呼ばれていたものです。それをより明確に提示する教理は、人々に安心や喜び、そして希望のうちに生きていく勇気を与えてくれるようなものであるはずです。しかしながら教理は、私たちの歴史や文化圏とはかけ離れた西欧でその主な発展を遂げてきました。その歴史的、文化的制約をもった教理の提示は、しばしばその大切な核心を見失わせる結果となる場合もありました。現代という時代の特徴は、文化的連続性を持つはずの西欧諸国においても、教理の貴重な意義が覆われて不分明なものなってしまうところにあります。
教理は、今生きている私たちにとって了解可能で、しかも自分にとって決定的に大切なものとして受けとめることができるようなものとして、再提示される必要があります。さらに西欧キリスト教文化においては決して取り上げられ、主題化されることのなかった、日本の文化的・宗教的な富(その精神性、慣習、知恵、悟り、道、信心など)が、いかに福音の核心と結びつくかを積極的に示していくことが肝要かと思います。
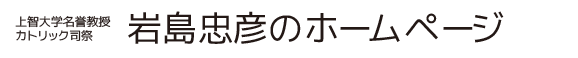

 聖なる普遍の教会を信じます
聖なる普遍の教会を信じます