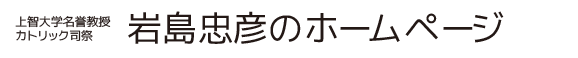時の節目
――新年によせて――
正月が来ると、いつも子供のころを思いだす。年が改まるとすべてが新しくなると本気で信じていた。大晦日の夜、枕元に新しいズボン、新しい下着などが置かれている。「明日起きれば上から下まで真っ新になる。自分自身も」。実際そのような心で新年を迎えることができた。子供のころは、次々と新しい体験をしていた。暑い夏に蝉を追いかけて一日中さまよった。杜の鎮守の暗い湿った地肌の上に無数のドングリを見つけた。初めて自転車に乗れた。父が映画に連れて行ってくれた、などなど。ある意味毎日が、新しかった。そうした一時一時は、古びることがなく、どこか永遠の輝きを保っていた。正月は特にそうだった。三が日は文字通り特別の日だった。日常を脱した遊びの日々だった。
大人になってからは、正月はそんな輝きを失ってしまった。大掃除をするでもなく、元旦を迎えても自室は散らかったまま。正月と言っても、昨日や一昨日とそれほど変わらない一日に過ぎない。昨日からの体の疲れは正直に今日も残っている。何かが新年から劇的に変わるわけでもない。時は流れる。
それでも私にとって正月は特別の時だ。たいてい私は近くの井草八幡宮に行く。地元の人がお神楽をやり、売店が立ち並び、おみくじの前に長い行列ができる。カトリック司祭である私が本殿で手を合わせるのも変なので、漠然と雰囲気を楽しみながら帰ってくる。普段はバスに乗る距離だが、ぶらぶらと歩いて家に帰る。
私には二つの暦がある。教会暦と世俗の暦である。教会暦は、「待降節」(クリスマス準備の4週間)で始まる。つまり11月末には、新しい年度が始まっているのである。これは私にとって神さまの暦であり、永遠の命の暦である。では正月で始まる世俗の暦は何か。私の実生活が生きられる時を示す暦である。私に限らず、多くの大人にとってこの暦による時は、ほっておくと止めどもなく流れていく。昨日に似た今日、今日に似た明日……。ある先輩の神父さんは、正月になると、「もうすぐクリスマスだな」と言うのが口癖だった。油断すると時はいくらでも流れていく。浦島太郎の話は、私たち一人ひとりの人生の物語であると思っている。「夢のよう」な竜宮城で過ごした数日間。戻ってお土産の玉手箱を開けたとたんに、白髪の老人となっていた。私たちの人生は長いようで短い。「面白おかしく」生きているうちに、気がつけば人生の黄昏時になっている。
キリスト教の信仰には、「体の復活」という信仰がある。一人ひとりの永遠の命は、魂だけでなく身体を伴って生きられるという教えである。これは、別の言い方をすれば、体を生きる今の世の生こそトータルな形で永遠の命の形を決定するのだということである。今の世での生き方がその人の器を決定する。その人の姿は死をもっていわば「完成品」となり、誰もそれに手を加えることができない。
するとどうか?この世の生の一時一時が、自分の永遠の命を紡ぎ出す「時の滴」であるということになる。この世の毎日が繰り返しの利かない大切な時となる。すると生きることが真剣なものとなる。誠実、よき業、人への思いやり、自分の人生を積極的に構築していくこと、運命を受容すること等々――こうした事柄がこの上もなく大切になってくる。こうして私たちは淡々と流れる時に棹さす必要がある。一時一時をできる限り、自分の手でしっかりとつかみ取る必要がある。自分の中の悪意や不正をできるだけ押さえ、惰性や御座なりな態度から脱したい。できるだけ「善き自分」を作り上げていきたい。
そんな決意を新たにするのが、お正月なのだろうと私は思っている。できることなら最後まで子供のころのみずみずしさを保って日々を過ごしたい。流れる時に意味を与えたい。そんな「時の節目」となるのがお正月である。今年は何が起こるのだろうか?楽しみである。
「だから、わたしたちは落胆しない。たといわたしたちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく」(2コリント4・16)。
![]()