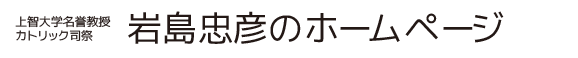『サン・オブ・ゴッド』観賞記
久しぶりに映画館に行った。年がら年中キリストについて語っているのだから、この映画は見ないわけにいかない。かつては『偉大な生涯の物語』とかゼフィレリの『ナザレのイエス』、さらには10年ほど前にはメル・ギブソンの『パッション』など、キリストについての映画が作られてきたが、最近はそんな風潮ではないと思っていた。しかしチャールトン・ヘストン主演の『十戒』以来のモーゼの映画『エクソダス』も上映中である。聖書の映画化は、ある程度のサイクルで繰り返されるらしい。
さて、本編である。最初と最後に福音書記者のヨハネが登場し、話しの展開を仕切る。「始めにみ言あり……」のヨハネ福音書の序文で始まり、全編はヨハネ福音書を主体として語られる。ニコデモの存在、マグダラのマリア、姦淫の最中につかまった女、ラザロの復活など、ヨハネ福音書に独特のエピソードが展開されていく。
とくにそれが顕著なのはイエスの受難を過越祭の前日(準備日)に設定していることである。これはヨハネ福音書に独自であり、他の三福音書(共観福音書)はすべて過越祭当日の出来事としている。共観福音書に従えば、最後の晩餐は過越しの食事であり、ユダヤ教が延々と祝ってきた原点としてのモーゼの契約を、最後の晩餐で新しい契約(新約)として書き換えた出来事であるということになる。ユダヤ教の一日は日没と共に始まるから、イエスの受難と死は、その日のうちの出来事となる。こうして晩餐は主キリストの十字架の意味を明白に語り、その実体は彼の受難史が語っている。両者は互いに説明し合っているのである。
ところがヨハネ福音書によれば最後の晩餐も受難も過越しの準備日(前日)となっている。その日に何があるのか?神殿で過越祭に食卓に供される子羊が屠られる日である。だからこそヨハネ福音書では、洗礼者ヨハネがイエスを指して最初から「見よ、神の小羊」(ヨハネ1:36)と言うのであり、イエスの死にあたっては「その骨はくだかれないであろう」(同19:36)という点を強調している。過越しの食事で供される「子羊は傷のないもの」(出エジプト11:5)でなければならないと規定されているからである。するとどうなるのか?ヨハネはイエスの受難と死の出来事そのものが「新しい過越し」であると強調し、共観福音書は最後の晩餐こそが「旧い過越し」を「新しい過越し」「新しい契約」へと刷新したということになる。この観点の違いは本質的に同一のことを指し示している。晩餐の実体は受難と死にあり、その意味づけは晩餐にあるからである。
映画は過越祭の前日というヨハネ説を採り、それを政治的に解釈している。映画中で大祭司カヤファは過越祭が無事に祝われるために、「イエスの案件」を前日中に処理してしまおうとしている。このあたりけっこう説得力があり、カヤファは登場人物の中でも存在感を示している者の一人である。
映画はヨハネ福音書を軸としているとは言え、他の福音書のエピソードをも取り込み膨らませている。たとえば十字架上の七つの言葉が発せられるが、これもできるだけ無理なく処理している。
ディオゴ・モルガド演じるイエスは好感が持てる。イエスがどのような人にも同じ好意の目線で近づき、笑顔を示し、自分の中に迎え入れている。イエスの活動の特徴がよく示されているのである。もう一つ、受難と死の描写はそれなりに過激であるが、十字架の出来事というものがそのようなもの以外の何ものでもないことを示している。十字架はキリスト教のシンボルとなったが、時としてキリスト教徒もその生々しさを忘れてしまうことがある。この点ではメル・ギブソンの『パッション』は鞭打ちの過酷さを余すところなく描いている。
『サン・オブ・ゴッド』は、すぐれたキリスト映画である。今日聖書学が格段に発展しており、あまり無理なドラマを持ち込むことはできない。映画制作者もこのことを弁えているようで、あくまで聖書に忠実に淡々と描いている。それでも、最終的にこうした映画に付きものの「違和感」は残る。これは映像が示しうるものの限界であろう。神のみ言葉である聖書と同じ深みを一本の映画が描ききることはできない。
さらに、この「違和感」の根には当時と現代とのギャップがある。「当時」をできるだけリアルに再現しようとすればするほど、今生きる自分との時間差を痛感する。映画は映画、今生きるのは自分。昔から、キリスト者は「もう一人のキリスト」と呼ばれていた。今の世にキリストを解き放つのは他ならぬ自分であるということだ。それは表面的な「まねごと」の次元の問題ではない。パウロは言う、「生きているのは、もはや、わたしではない。キリストが、わたしのうちに生きておられるのである」(ガラテア2:20)。
![]()