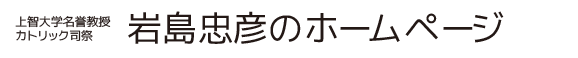「からだの復活を信じます」(使徒信条)
先日、母が100歳で亡くなった。
亡くなったのは3月13日の金曜日である。前日の木曜日、三年半前に死んだ兄の連れ合いが母を見舞い、さらにその日、姉も見舞った。用事がつまっていたわたしは、迷ったが、前倒しして金曜に神戸に向かった。世話になっているカトリックの老人ホームで母と対面したのは、ちょうど昼の12時だった。
荒い苦しそうな息をしていたが、わたしが来たことを告げると、はっきりと分かったようである。わたしは、これまで口にしたことのない言葉を母にかけた。「ありがとう、これまでのすべてにありがとう」と。そして「ご苦労さまでした」と言った。母に通じたと思っている。やがて呼吸がゆっくりとなっていった。だんだん間があいて、やがて止まった。12時30分だった。母は末っ子のわたしが駆けつけてくるまで、待っていてくれたのだろう。これでやることはやった、そんな感じで息を引き取った。
亡くなった直後の母を見つめて、最初に感じたのは、この人の命はここで終わりではない、終わるはずがない、という実感だった。大正3年生まれ、百年の様々な時期を生き抜いた体がここにある。それがここで終わり、ただ無に帰してしまうということは、決してあり得ないと感じたのである。
わたしの記憶にある母は、いつも苦労をしていた。父は49歳で亡くなった。母はそのとき、40歳そこそこだっただろう。母の故郷である神戸に戻り、部屋貸しをしながら3人の子を自力で養った。兄は大学生、姉は高校生、末っ子のわたしは小学校五年生であった。やがて兄は画家となり、スペインやパリで過ごすようになった。姉は結婚して子宝に恵まれた。わたしはイエズス会(修道会)に入り家を出た。いわば「出家」である。その間、母はわたしたちそれぞれの成り行きを眺める他なかったと思う。
親という字は、木に立っている(あぶなっかしい)子供を見ると書く。それぞれの子供が歩む道に口出しするでもなく、それでも見守り続ける――それが母の役割だったように思う。こうした母の人生を思うと、どちらかと言えば苦労の連続だった。幼少期に両親を亡くして以来、ずっとのことである。
母は頑張り屋でもあった。今の神戸高校の前身である兵庫県立第一神戸高等女学校では、がむしゃらに勉学に打ち込んだようである。その後、パルモワ学院で英会話・英文速記・邦文速記などを習得したそうである。20歳そこそこで銀行員の父と結婚し、東京を皮切りに、熊本・姫路・松山・高松・広島・豊中・尾張一宮と転々とし、父の死を期に生まれ育った神戸に帰ったのである。
これらすべてを振り返ってみても、やはり母の生涯の第一の特徴は「苦労」であったように思う。しかし、苦労はしたが幸せでなかったとも思わない。100年の歳月、自分の人生を精一杯行き切ったと言えよう。
臨終のときの話に戻ろう。わたしが最初に思ったこと――この生涯が今無に帰し、何の意味も結論も結ばないということは考えられない。わたしが中学からミッションスクールに通い出してから、母はカトリックの洗礼を受けた。以来死ぬまで、堅くこの信仰に留まってきた。わたしの方は、修道司祭となって、この母の通夜・葬儀・骨上げの一切を主宰することになった。
古来からのキリスト教信仰の要諦を約めた使徒信条は、「からだの復活、永遠のいのちを信じます」で終わっている。母の100年の人生は、永遠のいのちの中で確固とした意義を持ち、母の人格はその中で輝いていると思う。これがキリスト教独自の「からだの復活」の信仰であろう。
今、わたしの小さな寝室の本棚の上に母の遺骨が遺影と共に置いてある。不思議な感覚がある。生きているときよりも、今の方が母が身近に感じられる。初めての経験である。「からだの復活」の信仰の意味が前より分かった気がする。日本の習慣に従って、四十九日前後に、母が望んでいた、四ッ谷の聖イグナチオ教会に納骨するつもりである。わたしもやがて同じクリュプタ(地下聖堂)に入ることになっている。
![]()