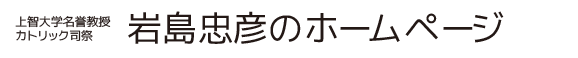聖心の信心をひろめ……
聖イグナチオ教会のクリュプタ(地下聖堂)には、聖心(みこころ)のイエス像がある。建て直す前には、大聖堂正面の祭壇脇にあったものである。イエス像なのだが、胸の部分にむき出しの心臓があり、その心臓はイバラに囲まれ、さらに炎がそこから噴き出している。多分私たち日本人にとっては、少々生々しすぎる感があるが、聖心の信心は、西欧では何百年も続いた代表的イエスへの信心の発露である。
聖心への信心はすでに中世にその発端があるようだが、16世紀以降その重要性が増し、聖母訪問会のシスターである聖マリア・マルガリータ・アラコックへの聖心のご出現、彼女の指導をしたイエズス会の司祭聖クロード・ド・ラ・コロンビエールの存在がこの信心を決定的にした。17世紀のことである。19世紀には聖心の祝日は教会全体の大祝日とされた。かくして6月は聖心に捧げられた月とされ、「聖体の祝日」の次の金曜日を「聖心の祝日」として全世界で祝われることとなった。
最も広く普及している「不思議のメダイ」の裏面には二つのハートが刻まれている。右側が剣で貫かれたマリアのハートであり、左側がイエスの聖心である。私が所属しているイエズス会はこの信心と固く結ばれている。私のいる上石神井修道院では、ほとんど毎夕「召し出しを求める祈り」を唱えるが、その最後の言葉は、「聖心の信心をひろめ、あなたが尊い血をもってあがなわれた人々に、救いをもたらすことができるようお導き下さい」となっている。
聖心の信心の核心はどこにあるのだろうか?『現代世界憲章』に次の言葉がある。「キリストは人間の手をもって働き、人間の知性をもって考え、人間の意志をもって行動し、人間の心をもって愛した」(22項)。神から遣わされた方であるが、私たちと全く同じ条件の中で、神さまの姿を、そしてその究極的愛の姿を示したのである。人の中心は知性でも意志でもなく、その人のハートである。人が何を感じ、どう行動するかは、その人の心の中心にかかっている。イエスの心を思え――これが聖心の信心の言おうとすることである。彼の心は、炎のように燃えあがっていた。彼の心は、その純粋さゆえに、常に周りからの妨害に遭い、深い痛みを感じていた。まるで心臓に絡みつくイバラのように。こうしたイエスの心を思うとき、私たちはイエスの愛の、そして神さまの愛の深みと質をかいま見るのである。神は高みから私たちを愛されたのではない。イエスは悩み、苦悩し、痛みを感じながらも、燃える心を持って前に進まれた――父なる神の愛をあかしするために。十字架の神学者であるE・ユンゲルは「神は、キリストを通して、人間の死を体験した。人の死苦を自ら知っている」とさえ言っている。私たちがキリストを知り、キリストを信じるというのなら、キリストの教えや行いを越えて、彼のふるえるような心にまで思いを馳せよ。ここにイエスの聖心の意味するものがある。
かつて『聖心の使徒』という雑誌があった。イエズス会のチースリック神父さんが、長年一人で編集責任をとっておられた。五十年以上前、私は指導の神父さんに勧められて記事を投稿した。まだ学生であった私は、自分の書いたものが初めて活字になったこと、稿料3000円をもらったことが嬉しかった。そのときの指導司祭が私に教えてくれたのが聖心の信心だったのである。そのとき、キリストの愛、そして父なる神の愛の核心が分かったように思った。以来、直接聖心について語ったり書いたりすることはほとんどなかった。しかしそのとき感じたものは今も自分の信仰理解の中心にある。共同体で「聖心の信心をひろめ……」という言葉を唱えるとき、いつも特別の思い入れをもって祈っている。
「さて、わたしたちには、もろもろの天をとおって行かれた大祭司なる神の子イエスがいますのであるから、わたしたちの告白する信仰をかたく守ろうではないか。この大祭司は、わたしたちの弱さを思いやることのできないようなかたではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて、わたしたちと同じように試錬に会われたのである。だから、わたしたちは、あわれみを受け、また、恵みにあずかって時機を得た助けを受けるために、はばかることなく恵みの御座に近づこうではないか」(ヘブ4・14-16)。私たち一人ひとりは、自分の弱さも欠点も思いやって下さる仲介者キリストを天に持っているのである。
![]()