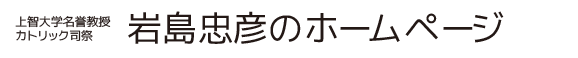少年時代
70歳をすぎると、やはり過去を思い出すことが増える。自分の小さい頃のことを思うままに書いてみたい。「随想」だからこれも許されるだろう。何で人の思い出話など読まねばならないのか、と思う方はパスしていただきたい。
私のプロフィールは、必ず「1943年姫路で生まれる」で始まる。だから時々、「私も姫路に住んだことがあります」とか「姫路はいい町ですね」とか言われる。しかし生まれただけで、何の記憶もない。多分、生まれて間もなく次の父の転勤地、松山に越したのだろう。私の最初の記憶は、防空壕に入った光景である。多分1歳前後のことだろう。庭の隅に防空壕があり、家からそこへと降りていく際、前を流れる川が見えた。暗く狭い防空壕に入って、家族の者でかたまっていた。それが私の一番古い記憶である。恐怖心とか危機感といった感覚はなかった。
幼年時代の記憶のほとんどは断片的で、バラバラの写真のようだ。ただセピア色の古写真ではなく。たいてい鮮明なものである。高松にいた頃、韓国と朝鮮民主主義人民共和国との領土争いが苛烈であった。ラジオは、毎日のように戦況の変化を伝えていた。近所の子供たちとラジオニュースのまねをして、「38度線を越え……」と繰り返していた自分を思い出す。
その後広島に移った。5歳前後だったのだろうか。母親と並んで原爆ドームの脇を二人で歩いている光景をはっきりと思い出す。周りは一面ススキが覆っており、私の背丈を超えるような高さだった。この広島で小学校に上がった。戦後間もなくでもあり、幼稚園に行ったことのない私にとっては、子供ばかりの団体生活に違和感を持っていた。自宅は翠町にあり、そこから皆見小学校へ通った。子供の私にとって30分の道のりだった。周りはほとんど田んぼで、途中大きな蓮池があった。大きな蓮の葉の真ん中をちぎってコートのようにはおり、ちぎった葉を帽子代わりにかぶって遊んでいた。
豊中で小5の姉が亡くなった。風邪をこじらせた肺炎だった。この姉はプックラ太っていて、ちょっと欲張りだった。しかし病気になってからは無欲になり、自分のものを何でも私にくれるようにいなっていった。やがて名古屋というか尾張一宮へ転勤となったとき、父は一人で先に任地に行った。家族で列車に乗ると、一人足りないと感じるのがイヤだったからだそうだ。
一宮に住んだのは、多分小3から小5位の2年半くらいだったのだろう。この期間は、私にとって自然と過ごす貴重な時期となったと、今までも思っている。家の周り50メートルはどこも田んぼで、学校から帰るときは田んぼの間の一本道を家まで歩いていった。引っ越した夜(6月頃だったか)、周り全体から蛙の合唱が聞こえてきたときは、家族みんなで心底驚いた。田植え前の田んぼでは、一面れんげが生えており、その美しさは今も心に残っている。田んぼと畦道、点在する鎮守の森、そこから夕方になると飛び立つ数多くのコウモリ、流れる小川。そんな中で、どんぐりを拾い、蛙やドジョウを捕って過ごしていた。一宮へは、それから一度も行っていない。あの原風景はたぶんどこにも残っていないのではなかろうか。
父親が亡くなった。49歳、直腸がんだった。私たちは一宮を引きあげ、母方の親戚が多い神戸へと移った。私が小5のときであった。ちなみに兄は大学生、姉は高校生だった。私は末っ子だったのである。母はそのとき40を幾つも出ていなかったのだろう。田舎では遊んでいても成績を維持できていたが、神戸の小学校に行ったら成績が落ちた。当時、地区の中学校で暴力事件が起き、新聞沙汰にもなった。「あそこだけはやめよう」ということで、ミッションスクールの六甲学院を受験することとなった。成績が落ちていたものだから塾に通った。6年生の冬の期間である。そろばん塾の先生が、塾が終わってから個人教授してくれた。真夜中に帰るものだから、通り道の警察に呼び止められたこともある。オリオン座という星座を冬空に仰ぎ見たことを忘れない。
六甲学院はイエズス会員が経営する学校で、当時は最低15人位は校内の修道院に居住しておられた。学校は「スパルタ教育」などと言われていた。「宗教」という科目があり、『偉大なる人間』『善き社会人』といった教科書が使われていた。そこで語られていたことは、理性、意思、善悪の価値観、良心、責任、自由といったことだった。こういう様々な言葉にはそれまであまり触れたことがなかったが、外国人の神父さんの説明はいちいち心に刺さった。自分の中にある後ろめたさみたいなものも感じた。
学校教育の中にキリスト教を持ち込まない――これが当時の校長の方針だった。校舎内には十字架一つさえ見出されなかった。しかし放課後、それぞれの神父さんは「別館」で、学年毎にキリスト教要理を教えていた。当時、生徒が一番洗礼を受けるのは中3のクリスマスだった。同級生たちも多くは、そのときに洗礼を受けた。母も受けた。私はしばらくは躊躇していたが、季節外れの高1の6月20日、もう一人の仲間と二人で、修道院の小さなチャペルで受洗した。式は簡素だったが荘厳で、祭壇へと進むとき、大切な一歩を踏み出すのだと意識した。
洗礼を受けたとき、これは他のことと異なって、一生本気で関わるべきことであると思った。事実、その時からイエズス会への召し出しを考え続け、やがて二十歳で修道院に入り、司祭になり、今日に至っている。この今の私にとって、防空壕の記憶や飛び交うコウモリの風景が何を意味しているのかは分からない。はっきりしていることは、そのどれも今の私の一部分である、ということである。
もう一つ、強烈に記憶に残っていることがある。たぶん小6の頃だろう。一宮時代から昆虫採集にはまっていた私は、真夏のふだん行かない住宅街の坂道に立っていた。アブラゼミでなく、クマゼミを取ろうとしていたのだろう。酷暑の中で立っている自分、なぜそこにいるのかとふと思った。それだけのことである。しかし忘れることがない。最近ある人が私に「自分はすべてが必然であると思っている」と言ったことがある。私は決定論者でもなければ運命論者でもない。しかし、私の少年時代が今の私を作り上げていることは間違いない。
![]()