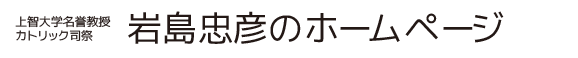夏休み
皆さんはヨゼフ・ピーパーという名前を聞いたことがあるだろうか。私がドイツのミュンスターで神学を学んでいた頃、同じ町の湖の反対側に住んでいた哲学者である。彼は50年以上前に『余暇と祝祭』という書を出しており、日本語にも翻訳されている(講談社学術文庫)。以下、彼の余暇、つまりレジャーについての考えを紹介しよう(以下、主にd.hatena.ne.jp/loisil-space/20070818/p1を参照した)。
ピーパーは、まず現代社会が、労働に過大評価を与えているというところから出発する.今日、労働という概念が人の生活の全領域を占めており、その価値観の周りを巡って休暇なども意味づけられる。たとえば哲学の営みといったものさえも、精神的労働として位置付けられる。われわれにピンと来る言い方に変えれば「仕事第一」と言ってもよい。しかしこのような位置付けは、近世以降のものであり、古代や中世において、労働と余暇は真逆の価値を持っていた。たとえば、中世のスコラ学は、ギリシア語のスコレー(暇)に由来し、精神活動や自己充実にあてることのできる積極的な意味をもった時間、また、個人が自由または主体的に使うことをゆるされた時間のことである(ウィキペディア参照)。つまり余暇は人間の個とその自由を展開できる本来の場であり、労働は他から強いられて自主性を失った状態ということになる。
労働を主軸とする価値観を持つ現代では、「余暇」はさしあたり「怠惰」と同義になる。しかし元来、現実との(労働とは)別の関わり方を、余暇は示している。効率や結果を目指して行動する労働と異なり、別の形で現実と関わる――それこそ、人間らしい、人間本来の姿であるというのである。
ピーパーは、そのような人間のあり方の典型として「祝祭」をあげる。「礼拝に根ざす祝祭」、そこに「余暇」の原点がある。キリスト教で言えば、さしあたり「ミサ」であろう。日本各地に固有の様々な「祭り」もそうであろう。そうしたものが、「人間が、何物にもおびやかされることなく、真実に人間的に生きることのできる空間」であると言うのである。ピーパーは、ますます人が作り出す、人為的価値のみが重要視される時代が到来することを見越して、このような著作をしたように思われる。そう言えば、チャップリンの『モダーン・タイムス』では、歯車の間で働いている労働者が、やがて歯車の中に吸い込まれていく様が、コミカルに描かれている。根に似たような時代批判があるように思う。
生産性を第一にする現代世界では、彼らの予告した非人間的な社会システムがますます強固なものになってきているように思う。より早い移動手段を追求し、より効き目のある薬品を開発し、より美しく見える化粧品を考案しようとする。こうした試みには限度がないように思われる。そしてそれらを支えているのは、従事する人々の必死の努力である。こうした今日の傾向は、人間をより幸せにするのか。誰も簡単には答えられない。いずれにせよ、このような方向性は当分変わることがないであろう。
そこで、多くの人々は自分が従事する「仕事」の中に、自分の生きがいを見つけ出そうとする。たぶんそれも間違ってはいない。自分の職業や技能への誇りが生まれる。ただし、それが自分の存在意義への根本的な答えを与えてくれるものかと言えば、やはり疑問である。ピーパーはより奥の人間性の問題を見つめているのだろう。
目下、子供たちは夏休みの中にいる。大人はそれほど長い休暇を取ることはできないだろうが、それでも自分の子供に数日でもつきあおうとすることだろう。われわれの遠い記憶にもあるように、夏休みには、ふだんと異なった時間が流れる。そしてそうした記憶が人生の中でも貴重なものとして残る場合が多い。モノを作ることだけが能でない。この夏は、普段と違った周りの世界との関わりを味わってみたい。
![]()