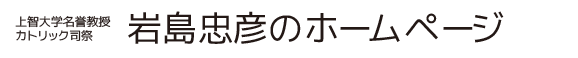神々と神
アルタミラの洞窟に、獣が描かれ、その横に人の手が書かれている。これは原始人が狩猟をしており、獲物を捕らえたいという願いが定着したものである。この人の「願い」は呪術的意味に解され、人の強い思いが祈りの形を取っている、というのである。言いたいことは宗教は人の歴史の中で最も原初的なものであるということである。どの民族の歴史においても酒と宗教は同じくらい古い。
それはやがて神話として定着し、神々と人との関わりが展開する。ギリシア・ローマ神話然り、古事記然りである。どうも多神教の方が、一神教よりも古いように思われる。日本では八百万の神が存在し、ギリシア神話では、ゼウスを頂点とする神々のピラミッドが構成されている(パンテオン)。
日本の場合、神の語源は相当に曖昧である。辞書によると、①カミ(上にあって尊ぶ)、②上身(人の上にあるもの)、③天照大神のカガミ、④明らかに照らす→アカミ(明見)、⑤カシコミオソル等々――かなりバラバラで出自が明確でない。『日本国語大辞典』(小学館)によると、「カミ」を次のように定義している。「宗教的、民族的信仰の対象。世に禍福をもたらし、人に加護や罰を与える霊威・古代人が、天地万物に宿り、それを支配していると考えた存在。自然物や自然現象に神秘的力を認めて畏怖し、信仰の対象としたもの」。これまた「定義」とは言えず、諸要素を叙述している感がある。
そんな中でなるほどと感じたのは、ギリシア語についての話である。ギリシア語で神はtheosである。最も初期のギリシア語でtheosは、次の特徴を持つそうだ。①呼格を持っていなかった、②述語として用いられたというのである。これをもう少し簡単に言えば、初期ギリシア語で「神」は、名詞として用いられず、いわば形容詞的に使われていた、ということになる。するとどうなるのか。「この景色はtheosである」とか「この木はtheosである」といった使い方になる。するとここで「神」は、「神々しい」とか「神秘的」といった言葉に近い。さらにその言葉は人間の原体験に根ざしているということになる。このように考えると、宗教や信心の発端も理解しやすい。通常経験の中で人は時として「神」を経験する。するとその場やモノが神的なものとされる。これは古今東西を問わず、どこにでも見られる現象である。鳥や動物が神的礼拝の対象となる場合もあれば、特定の場所が神域とされたり、ご神木が崇められる場合もある。こうなると日本の場合、たいていの宗教的施設、具体的には神社仏閣が特別の場所と見なされ、ふだん不信心な者もそうした場では手を合わせ、祈ることに抵抗がないのもうなずける。
そうすると人が様々な場所やモノにおいて「神的」な経験をするとすれば、それは「神」を経験する場が複数であるということにもなる。つまり経験上は「多神教」の方が自然であると言えるのではないか。そこに「一神教」を打ち出し、強い人格神のラインを敷いたのが、ユダヤ教であり、そこから派生したキリスト教およびイスラム教である。すべてを統べ治める神が複数存在すること自体が矛盾であり、絶対的存在者は唯一であると主張する。こうして宗教史の中では、多神教は宗教の中でより原始的形態、一神教がより洗練された形態と見なされるのが一般的である。このような評価は基本的には正しい。しかし多神教的発想が持つ人間の経験への近さには捨てがたいものがある。神は超越存在であり、人をも含むこの世の中には聖なるものはなに一つないとするなら、やがて人は超越者である神自体を自己の関心から閉め出すことにもなりかねない。一時「世俗化」という考えが哲学・神学の世界でキーワードとなった。この風潮は一時的で、やがてこの世俗礼賛の風潮は消えていった。
この世のものや出来事の中で、「神」を感じ取ることがなければ、人にとって宗教心が芽生えることはないだろう。そのためには「多神教」の示す豊かな世界を再評価すべきではないだろうか。「一神教」と「多神教」の関係――これはインカルチュレーションの課題である。日本における神道や仏教の伝統はこうした神的経験の遺産を、長年にわたって積み上げてきた。筆者はカトリック司祭であるが、このような遺産を共有することが、日本のキリスト教にとって大切なことではないかと思う。
![]()