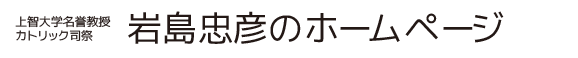二つの命を生きる
この30年余、カトリック入門講座を東京四ッ谷で毎年開講している。そこで常々言っていることがある。人は二つの命を生きる、ということである。一つは「この世の命」もう一つは「永遠の命」である。
若いころから司祭への道を歩み続けて、今や72歳になっている。いくら寿命が延びたとは言え、活動ができるのはせいぜい10年位だろうか。この世の命の長さも、あと20年ほどか。多く残されていない余命と考えても、相変わらずしゃばっ気は抜けない。入門講座の後で、近くのファミレスで参加者と雑談する。昨日も若い人たちが一緒で、「好きな女優と言えば、原節子とか香川京子なんかですか?」と訊かれて、ずいぶんと年寄り扱いされるようになったものだと思った。「そんなのは父親の世代のものだ、最近気になるのは有村架純といったところかな」と言うと呆れられた。
人間、この世に生きている限り一生懸命「この世」に関心を持ち、「この世」と取り組む。テレビ俳優のことだけではない。自分が長年関わってきたキリスト教神学についても、少しでも理解を深めようと思う。今年次々と開催された、ボッティチェリ展、ダヴィンチ展、カラヴァッジョ展もじっくりと観た。「それが何のためになるのか」と訊かれても分からない。でも、生きるということは、この世にあって「いいな」と思うものに向かい合うことだと思う。この世の事柄や周りの人々としっかり向き合い、自分のなすべきことをする――それが生きるということだろう。
それでも私たちのこの世の命は、過ぎてみると短い。キリスト教の歴史は二千年、文明の歴史は数千年、ネアンデルタール人や北京原人からは十万年ほど――こんなスケールにおいて見ると、私たちの命は歴史の流れの中で一瞬現れて消える泡ほどのものである。それでも一生懸命生きようとする。死ぬその日まで。
この百年そこそこの「この世の命」は、誰が「受け取る」のだろうか?どれほどはかない命であっても、自分にとってはかけがえのない命である。幼少時より死に至るまで積み上げてきた他ならない唯一の大切な命である。この私の命、誰が受け止めてくれるのか?配偶者か、子供か孫か、親友か。彼らの記憶に残る私は、私の命のごくごく一部であろう。それでは私丸ごと受け止めてくれるのは誰か?すぐに思いつくのは、「誰もいない」という答えだ。そうするとどうなる。私が積み上げた一生は宙に浮く。と言うより、無意味というレッテルを貼って廃棄されることになる。それでいいのか。いいはずがない。こうしたことが不条理というものである。道理に合わない――意味を成さない。
キリスト教の洗礼を受ける人は、「新たに神の子として生まれる」とか「永遠の命を生き始める」と言われる。それは死なない命、死線を越えて生きる命である。それは死んでから始まるのではない。生きている中で自分の永遠の命が始まるのである。今生きているこの世の命が否定されるのではない。それどころか、この世の命が私の永遠の命の形を決定するのである。これを「体の復活を信じます」という信仰告白が示している。この世で人は体を通してのみ生きている。精神ではなく体の復活、つまり永遠の生命は体を伴ったものとされている。それは、言い換えるとこの世で生きた私の生が丸ごと永遠化されるということなのだろう。そこに「私」のすべてがあるのだから。そうであれば、死ぬ日まで、人はこの世の生にしっかり向かい合い、子や孫を愛し気遣い続けることにも意味がある。それらすべてが、永遠の命の質を決定するからだ。
こうした考察の根幹は次の一点に集約される。神を信じるか信じないか、である。今の人間は、さしあたり自分と周りの世界との関係で、日々の命を紡いでいる。私とこの世。それ以外に何か考えるべきものがあるか。その他に考えることができるとしたら、神のみである。その他のものは結局この世の何かである。神のみがこの世のすべてを越えた存在。そしてこの世のすべて、つまり私の命をも丸ごと引き受けてくれる存在である。だから昔から「神は全知・全能・全善」と言われてきたのである。そのような神を信じるのか。信じないとするなら、人はまた自分とこの世だけに取り残される。それは不条理である。信じるとすれば、私とこの世とのすべての関わりは、永遠の価値を獲得する。神を信じるという立場だけが、「すべて」を無意味から救い上げる。
人は二つの命を生きている。しかもすでに「この世」において、「永遠の命」を生き始めているのである。
![]()