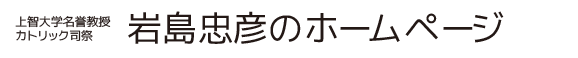『沈黙』について
マーティン・スコセッシ監督の『沈黙』を見てきた。『沈黙』は1971年篠田正浩監督が映画化しており、2度目の映画化である。スコセッシは若い頃司祭職を目指したこともあり、キリスト教信仰の問題はやはり彼の積年のテーマであったのだろう。そのことが特に表れているのは1988年の『最後の誘惑』だろう。十字架上で喘ぐキリストに最後の誘惑が襲う――ここから逃れて普通の人間として生きろ、と。その誘惑に従ったイエスは、マグダラのマリアと結婚し多くの子供を設け、平凡に生き普通の死を迎える。その間イエスは遠くからパウロが「キリストは私たちのために死に蘇り父の許へと還られた」と説いているのを眺める。いわば一種のパラレルストーリーである。しかしこの「普通のイエス」に生彩はなく、映画全体としてもあまり成功作とは思われなかった。
それ以来、スコセッシは遠藤周作の『沈黙』を紹介され、二十数年間構想を温め、昨年やっと映画化したのだそうである。舞台の中心は長崎のトモギ村と五島である。ポルトガルの宣教師セバスチャン・ロドリゴとフランシス・ガルベ神父は、彼らの師クリストヴァン・フェレイラを追って日本へ向かう。すでに日本は禁教の時代である。ガルベは信徒と共に殉教し、ロドリゴは最終的にフェレイラに出会う。彼は沢野忠庵と名乗り妻帯していた。棄教したのである。彼はロドリゴにも棄教を勧めるが、ロドリゴはこれをよしとしない。彼は監禁の身となった。ある日彼の目の前で数人の信徒が逆さ吊りになり、「お前が教えを捨てるなら、彼らを解放する」と言われる。ロドリゴは彼らを残虐な苦しみから解放するために自ら踏み絵を踏むのであった。この時、イエスの声が聞こえる、「踏むがいい。お前の足の痛さをこの私が一番よく知っている。踏むがいい。私はお前たちに踏まれるため、この世に生まれ、お前たちの痛さを分つため十字架を背負ったのだ」と。
遠藤の小説の表題となった沈黙という言葉は、この映画でも何度か繰り返される。神のためにこれほどまでに苦しみ堪え忍んでいるのに、神からは何の応えもない、一言の言葉も聞こえない――神からは沈黙、これがこの作品のテーマなのだろうと思う。この主題はアリだと思う。私たちが信仰に分け入っていっても、ゆきづまりを感じても、そうそう天からのお告げの声が聞けるわけではない。むしろ「神さまの声が聞こえた」などと言う人が出てきたら、「ちょっと怪しい」と思う方が普通である。
しかしこの作品の中では最後だけ、キリストの声がすると言うのである――「踏むがいい……」と。何で神は沈黙を守り続けたのに、キリストは最後にこれほど明瞭に声を発しているのだろうか。キリストの言葉ならば、天のおん父の言葉でもあろう。何で最後だけこのような声が聞こえるのだろう。私にはここに『沈黙』のしっくりしないものを感じるのである。新約聖書はイエスの言葉や行いを数多く集録している。福音書によって彼を描く角度が異なっているのも事実である。しかし聖書は同一のイエス・キリストを描き出している。そこには常に一種の強さ、一途さが表れ、それが父である神を指し示している。そうしたイエスの言動の横に『沈黙』の「踏むがいい……」を並べてみると違和感がある。聖書の示しているキリストがこのような屈積した言葉を発するとは思えない。
映画の中に一つのシーンがある。海辺の水たまりに自分の顔を映すロドリゴ、その顔が瞬間イエスの顔に変わる。彼は驚き、そして笑い出す。ここに「踏むがいい……」の言葉を解釈する鍵があるように思う。つまりこの言葉はイエスを伝えるためにこの地までやってきたロドリゴ自身の思いであり、決してイエス自身の思いではない。宣教師の心根はキリストの思いに通じ、時として同一のものと錯覚する場合もあろう。しかし宣教師も一人の人間である。イザヤなら、「天が地よりも高いように、わが道は、あなたがたの道よりも高く、わが思いは、あなたがたの思いよりも高い」(55・9)と言うだろう。ロドリゴが聞いた「イエスの声」は自分自身の心の叫びに他ならなかったのであり、それこそ「沈黙」というテーマからして一貫性がある。
スコセッシの『沈黙』はよくできた作品であり、登場人物それぞれの行動や決断も無理がなく、信憑性がある。「踏むがいい……」の言葉をキリストに帰していることの他は。スコセッシは『最後の誘惑』で、「普通の人イエス」を描こうとして挫折した。より巧妙に創り上げられているが、同じ挫折がイエスの言葉において露呈している。「踏むがいい。お前の足の痛さをこの私が一番よく知っている。踏むがいい。私はお前たちに踏まれるため、この世に生まれ、お前たちの痛さを分つため十字架を背負ったのだ」。芸術においてイエス・キリストを表現することは至難の業なのだろう。
蛇足だが、フェレイラは死を前にしてもう一度キリスト教へ立ち返ったという説もあるそうである(『日本切支丹宗門史』)。
![]()