新要理書の意義
岩島忠彦
『カトリック教会の教え』が刊行されて、ちょうど半年が経つ。第三刷ができて、二万冊が刷られたことになるそうだ。あまり大きくない教会の読者層を考えるとよく広がったと言えよう。筆者もその間、新要理書について講演をしたり研修会をしたりして、この書を歓迎する声、また懸念を表明する声と、さまざまな反応をも経験した。この機会に、新要理書の意義と限界について思うことを述べておきたい。
立体的な信仰の提示
『カトリック教会の教え』は日本司教団によって吟味され公認されたひさびさの要理書である。それは従来のものとは全く異なった新しいスタイルのものである。四名の主要な著者が、教理、典礼と秘跡、倫理、祈りの四分野におけるカトリック信仰の具体的内容を、それぞれの知識と理解に従って、総合的に提示している。信仰は人間の生である。だから現代という生の条件の中で具体的姿を取る。各部はこうしたことを反映して教会が生きてきた信仰の発露を「今」という時点から総括している。「教え」だけでない、生き方や祈りといった次元など、いわば四本の柱で立体的に構築されたカトリック信仰の提示である。本書を読むと、各部の執筆者の異なった傾向がかなり明白に察知される。悪く言えば、バラバラ。しかしそのために立体的な信仰提示がさらに際立っている結果ともなっている。
二つの要理書
このところ『カトリック教会のカテキズム』(ローマ新要理書)との関係や違いについての疑問がしばしば表明されている。両要理書はかなり違っている。ローマ要理書では教会の伝統が網羅されている感がある。各時代に教会はそれぞれの分野でどのようなことを教えてきたかが堅実にまとめられている。日本の要理書は、どちらかと言えば、こうした伝統を今どう受け止め、どう理解するべきなのかという点に力が注がれている。前者からは個々のことがらについて、結局どう理解し判断すればよいのかという疑問が出る。後者では書かれたことがどこまで教会の公式の教えであるのか、執筆者の個人的意見に過ぎないのではないかという疑義が時として生じてくる。それがまた両要理書の意義でもあり限界でもあると言えるのではなかろうか。
自主的な信仰を
にもかかわらず、筆者は日本の新要理書をお勧めしたい。一例を取ってみよう。原罪とその人類への伝播について、ローマ要理書は、アダムの罪が生殖によってすべての人に伝えられ、人は皆原初の聖性をもたずに生まれてくるといった伝統的教えを踏襲している。日本の要理書は、原罪の教えとそれがすべての人に伝わるとは一体どのような意味があり、私たちはそれをどう理解し受け止めることができるのかということを主眼として説明している。そこでの、「罪の社会的要因」「信仰前の恩恵の欠如」という説明は単に執筆者の個人的解釈ではなく、現代のカトリック神学のコンセンサスとなっているものでもある。「教え」が繰り返されても、それが理解されなければ信仰を喚起することは困難である。特に現代人にとって、特に非キリスト教的文化圏にある日本人にとって。
すでに洗礼を受けている信者にとってはどうであろうか。やはり、自分の受けた信仰内容をお題目のように大切にしているだけでは、自信のようなものがいつまでも生まれない。それが自分にとっての主体的な確信となっていかなければ、今の日本では受けた信仰そのものもやがてうやむやになってしまうことにもなりかねない。
そんな意味からも『カトリック教会の教え』を改めて推奨したいと思う。大部なものであるが、気軽にあちこちを拾い読みし、教会での研究会のグループなどで一緒になって信仰理解を深めるためのよすがとしていただきたい。
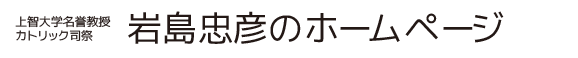

 教理の現在
教理の現在