地の面は新たにならん
岩島忠彦
聖霊刷新運動の隆盛
およそ百年前、アメリカのプロテスタント教会から始まったカリスマ運動は、一九六〇年代以降新たな聖霊刷新の運動として、カトリック教会をも含み、超教派的に世界的な広がりを見せている。これは、「聖霊の第三の波」などとも呼ばれているようだ。以来、聖霊における信仰の刷新を求める数々の信徒運動も生まれ、現在も盛んである。筆者に身近なところでは、上智大学でイエズス会の司祭が指導しながら長年、日曜日毎に祈りの集会が持たれている。通常の教会でのミサや信仰生活に飽き足りないでこうした集会に参加し、それまでにない生き生きとした信仰を再発見したような人を何人か知っている。
いちがいに「聖霊刷新運動」と言っても、かなり幅のあるもので、時として教会の制度を批判したり、その指導を拒否したりして、他の信徒たちの反感を買っている場合もある。
教会の魂である聖霊
聖霊降臨が教えるように、教会は、聖霊によって生まれ、聖霊においてのみ進み、存立し続けることができるものである。私たち一人ひとりの信者も、父と子の愛の絆である聖霊をいただいているからこそ、信仰することができているのだ。ヨハネ福音書はこれを、イエスが与えようとした「活ける水」と呼んでいる。それは、信じる者の内からわき上がる神のいのちの流れとなって、自身を、そして周辺を生かし続ける。祈りの中で、生活体験の中で、試練の中で、キリスト者はそれに触れる。それが信仰者の実存にとっていかに決定的に重要であるかは、千年以上にわたって構築されてきた広大な恩恵論神学が証している。微に入り細をうがち論じられてきた恩恵の種類や区別は、いかに信仰者が聖霊によって規定されているかを訴えている。公教要理においても、「成聖の恩恵」を受けることが信者となることの本質であると教えられてきた。聖霊の賜物を抜きにするなら、教会はイデオロギーに固まった一つの社会集団と区別することができないであろう。
今の信仰に必要なもの
筆者がここで問いかけたいのは、今日なぜこれほどまでに「聖霊刷新運動」が人の心をとらえるのか。また、それが元来、聖霊を命とする教会と時としてぶつかることがあるのかということである。四十年前に開催された第二ヴァティカン公会議は、現代における聖霊降臨の出来事と評価された。ところが、その後の刷新や現代化の動きの中で、教会は何やら大切なものを忘れつつあるのではないかという気がする。「わたしを離れては、あなたがたは何もできない」(ヨハ15・5)。公会議後の、いわゆる「改革派」も「保守派」も、教会の外的形態や活動、あるいは正統信仰の文言にばかりこだわって、教会の魂である聖霊の賜物につながり、生かしていただくという姿勢を忘れかけてはいないだろうか。聖霊刷新の新しい教派の中には「水の洗礼」と区別して「霊の洗礼」をより重んじる場合がある。その是非はここで論じないが、制度としての洗礼が空洞化しつつあるのではないかという問題提起がここに見られることは確かだろう。
現在の日本は不景気で元気がない。多くの人が生きる喜びを失って、精彩がない。教会にいると信者や司祭さえも、周りを照らすどころか、こんな雰囲気に自らも感染しているのではないかと思うことがある。「パンのみにて生きず」と言われているように、キリスト者であるなしにかかわらず、すべからく人間は、神さまからの命によって生かされ、生き始めないと幸せになれない。「主よ、聖霊を遣わしたまえ。しかしてよろずのものは造られん。地の面は新たにならん」。昔から唱えられてきたこの「聖霊降臨節の祈」を今こそ唱えたい。そしてまずはこの私に霊のあふれる恵みを願いたい。
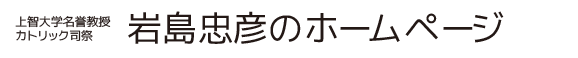

 書評:「インカルチュレーション...
書評:「インカルチュレーション...