インカルチュレーション事始
岩島忠彦
注目すべき一冊である。「妖怪の棲む教会」というエキセントリックな書名に惑わされないで、できるだけ多くの信者さんに読んでいただきたい。著者である大阪教区司祭中川明師が私の研究室を訪ねてきて、「今関心があるのは『妖怪』ということなんです」と話していったのはもう何年前だろうか。とつとつと語る彼の口からは、やたらと「異人」とか「妖怪」といった言葉が飛び出してきた。当時の私はそうした言葉が、あまりにも漠然としており、失礼ながら「思い入れの強いタコツボ思想かな」などと思ったものである。しかし今回、中川師の原稿を通読して、新鮮な驚きを感じた。彼は司祭として生きながら、キャッチフレーズやスローガンに逃げることなく、日本人がキリスト教を信仰すること、また日本の教会がどうあるべきかを考え続け、個人的な思いこみの次元を脱したある程度の方向性を示しているのである。まずは、その内容を紹介しよう。
本書は三部から成っている。第一部「ゆきづまった日本の教会」では、戦後日本のカトリック教会の歩みを多くの図表を用いて分析している。外国人・邦人司祭数と年齢分布の推移、成人受洗者数の推移などを見、その間教会がどのような時期を辿ってきたかを読むと、私たち教会が置かれた現状が説得力をもって迫ってくる。著者はとくにナイス1に注目し、そこで確認されたことがいかに重要であるかと同時に、謳い文句がどれほど無力であるかを指摘している。むしろ教会内に「保守派」「社会派」といったレッテルの張りあいを生み、「不協和音」を生んでしまったと言う。第一部の結論として著者は、「海外からの援助に依存する体質からの脱却」「閉じこもり体質からの脱却」「教会内部の不協和音の克服」の三つをこれからの課題にあげている。著者は表面的なスローガンや特定の「理論」に固執することなく、多様な教会の現実を多角的に、いわば「複眼的に」眺めて冷静に今のカトリック教会を理解しようとしている。第一部だけでもお勧めである。
第二部、第三部では「救い」について掘り下げ、第一部で述べた三つの課題に共通する問題の根に迫ろうとしている。第二部「『救い』の場を求めて」は、自分の期待を挫こうとする「頑固な現実」と直面することをとおして、自分の慣れ親しんだ狭い視野を打破しなければならないとの主張から始まる。それを通して、人は「コンパッション(共感)」を獲得することができ、「救い」ないし「救いへの希望」を実感できるのであるとする。この「頑固な現実」は「他人」とか「他」などという言葉に置きかえられていき、貧しいフィリピンや戦時下の沖縄人、在日勧告朝鮮人などのエピソードが語られ、他方、「富んだ」現代日本人の病巣が分かりやすく(図式を用いて)示されている。著者は、人が「救われる」ためには、「傷つく可能性」を通らざるをえないとする。本書で唯一と思われるイエスの言葉の引用(「金持ちが神の国に入るよりも、らくだが針の穴を通る方がまだ易しい」)が突如リアリティをもって迫ってくる。
第三部「『救い』をもたらす場としての『妖怪の棲む教会』」では、「頑固な現実」「他人」「他」が「異人」「妖怪」と置きかえられる。この置きかえは、「他」の持つ、不気味さ・脅威感をクローズアップする。著者は、特定の社会集団が「異人・妖怪」を駆逐・敬遠するメカニズムを示し、教会もその例外でないとする。その上で、「キョウカイ(境界)の上に教会を建てよう」と冗談まがいのことを言う。しかしそれは冗談ではなく、本書の結論のようなものなのである。第一部で共依存症とさえ言われた閉じこもり体質を捨てて、自分にとっての周辺的存在(「異人」)と接してこそ、教会はイエスの教会になれるのだと言うのである。本書は、神ご自身が、私たちにとっての「妖怪」の最たるものであるという指摘で終わっている。
いちおうのまとめはしてみたものの、本書の魅力・説得力を示すことはできない。この本が理論の本ではないからである。著者がサラリーマンとして生き、西欧神学を学び、庶民的な小教区の司牧を積み重ね、中央協議会で広汎なデータに触れ、そのような中で、自分の中から芽生えた問いと取り組む何十年かのプロセスが本書の中で結晶している。個々の理解を助けるための民俗学者や宗教学者の理論が援用されているが、それにふりまわされてはいない。まして従来の西欧神学の受け売りはない。まあ一言で言えば、自分が現実を見つめて悪戦苦闘してきた中から生まれた、セカンドハンドでないオリジナルである。それを数多くのエピソードや体験談で示そうとしている。「最近、『物語』に惹かれます」と著者が言うように、この本も物語神学である。西欧キリスト教神学は論理を主とする思弁神学が主流であった。その弱点は、抽象の網をもれる具体的事実と個別の関心を無視してしまうことにある。現実をありのままに眺め、人を鼓舞するには「物語」という形でなければならない。こうして西欧でも最近「物語神学」の重要性が主張されてきている。「物語」は物語られ、読んだり聞いたりされる以外にない。「要約」などできないのである。
「インカルチュレーション」について論じられ始めてから、もう何十年もたつ。しかし私は、この言葉を読んだり聞いたりするのにうんざりしている。すべてインカルチュレーションについてとか、その重要性についてといった一般論の繰り返しであり、効き目のないお題目のようになってしまっているからである。冒頭で「注目すべき一冊」と言ったのはお愛想ではない。はじめて「インカルチュレーション」の努力に出会ったと思ったからである。著者は、信仰の意味、教会の存在意義を自分の言葉で模索している。それは自分の文化背景に位置づけてということである。だから迫力がある、説得力がある。本書にはカトリック以外では理解されない特殊用語はほとんど使われていない。通常の日本語で勝負しているのである。得られた結論などは実は前々から分かっていることである。それは「十字架の精神」であり「愛の掟」である。しかし、それが私たちが生きている具体的環境・精神風土に即して導き出されているために力をもっている。
著者も認めるように、本書は必ずしも完成度が高いものではない。個々の叙述や論の展開が必ずしもスムーズでなく、用例がピタリと決まっていない所もある。「異人」「妖怪」という言葉は非常に興味深いが、そのまま教会の特質を示す言葉として定着しうるかと言えば異論もあろう。またそこから出された提言「キョウカイ(境界)の上に教会を建てる」ということが何を意味しているか、これからの日本の教会の具体像としてもうちょっと書いてもらいたかったなどとも思う。つまり荒削りではある。しかし(日本カトリック出版界において、また、私が知っている範囲では)本邦初のインカルチュレーションものである。西欧の神学で養われてきた私には悔しいけれど書けないものである。しかしこれを機に、色々な人が受け売りや出来合いに逃げない信仰論や教会論に挑戦して欲しいものである。とにかく、まずは読んでみてほしい。それほど難しくはないはずだ。
著者は「あとがき」で、「ヴィジョン」ということに疑問を持ちだしたと言い、「無理なものを無理して生み出そうとするならそれは嘘になる」と述べている。そしてステンドグラスの個別部分にたとえて、「絵という『全体構想』がない場合、個々のガラス片の美しさ、『ガラス溶塊の質』が極めて重要になってくるだろう」とする。同感である。 (この書評は、カトリック新聞掲載の元となったより詳細なものです)
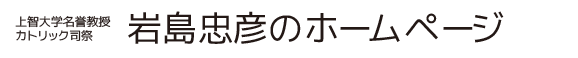

 グローバル・スタンダードの信仰...
グローバル・スタンダードの信仰...