世紀末を越えるために
岩島忠彦
一九九九年、復活祭。復活祭は、光と命の勝利の祭典、キリスト教信仰の喜びを高らかに謳う日です。しかし、今の社会と私たちの心はそのような雰囲気にすなおに共鳴するでしょうか。一千年代最後の年にあたって、個人も社会もむしろ行きづまりとある種の閉塞状態を感じ取っているのではないでしょうか。二〇〇〇年になれば新しい見通しが開けると期待している人もあまりいません。一体私たちはどんな時代に立っているのでしょうか。人類はどこに向かっているのでしょうか。
「進歩と発展」。こういったキャッチフレーズを疑わず、輝かしい未来を夢見て、人は最近まで歩んできました。ところが思い描いた高度の科学技術社会がほぼ実現した現在、このような「進歩」が、人を必ずしも幸せにするわけでもないことに気づきました。生きていることの意味、幸せとは何か、命のゆくえ、そして歴史はどこに向かっているのか。現代文明は、それらに何一つ答えないどころか、より混迷をもたらしたように思われます。「人はパンのみにて生きず」。物質文明とも呼ばれる今の時代にあって、私たちはこの聖句の意味を、かつてない規模で味わわされています。
第二ヴァティカン公会議は、精神的貧困に苦しむ世界を福音の力をもって救いたいとの意図をもって開催されました。神学は福音の示す「希望」(モルトマン)を標榜して今の時代に呼びかけました。しかし、徒労感に打ちひしがれた現代人にどれほどの響きがあったでしょうか。「人間の良心に強い影響を及ぼし得る福音のかくれた力は現代どうなっているのでしょうか」(『福音宣教』)。一九七五年のパウロ六世のこの叫びは、今も変わらず続いているように思われます。
現代人の無力感は、超越の次元を切り捨ててすべてを自分でとり仕切ろうとする人間の自負心に端を発していると思われます。近世以降、人は人間が歴史を導き、歴史を創り出していくのだと信じて進んできました。しかし今や、自分が築いてきた過去にも、現在にも、そしてまた未来に対しても責任が取りきれないと痛感しています。これに対して福音は、神が歴史を導かれるのであって、人間はこれに共鳴し協同していくのであるという見方を教えています。創造の教えは、無機質なビッグバン・セオリーなどではなく、神にイニシアティヴをもつ意味ある世界の初めについて語り、キリストは神の愛が例外なくすべての人を救いへ導いてくださると教えられます。そしてまた、終末の教えは、神が人間をも含む森羅万象すべてを完成に導くことによって時間の充満を迎えることができると約束しています。信仰宣言は「からだの復活、永遠のいのちを信じます」と述べ、黙示録では、その時神は「人の目から涙を全くぬぐい取ってくださる。もはや、死もなく、悲しみも、叫びも、痛みもない」(黙示録21・4)と語っています。人類の歴史は、慈しみに満ち、かつ全能である方への信頼においてだけ、希望のうちに進んでいくことができるのではないでしょうか。
一九九九年、教皇様はこの年を「おん父の年」とされました。あくなき人間の自立心は、人をこの地上でみなしご状態にしてしまいました。多くの人が、生きる指針を見失い、とまどい、意気阻喪し、立ち往生しているかのようです。長い歴史の教訓の後、私たち人間は、もう一度、神の前での謙虚な生き方を学び始めるべきではないでしょうか。新たな世紀を迎えるために。「わたしは、あなたがたをみなしごにはしておかない。あなたがたのところに戻って来る」(ヨハネ14・18)。
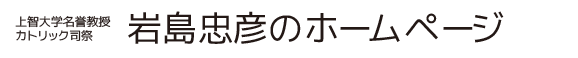

 聖体大会と聖体への信心
聖体大会と聖体への信心