公会議はなぜ必要だったのか
岩島忠彦
公会議以前の教会
読者の半数の方々は公会議以前の教会を体験された方々ではなかろうか。筆者もまたその一人である。ローマンカラーの司祭の凛とした立ち居ふるまいの奥に、静寂なる永遠の世界とでもいうべき教会を感じ取ることができた。変わることのないカトリックの教えと道徳、世界中同じラテン語で執行されるミサ、天使の声を思わせるグレゴリアン聖歌。今でも当時の教会の雰囲気を思い出すと、なつかしさと安らぎの想いがよみがえってくる。このような懐古の情を胸中に宿している方々も数多いのではないだろうか。なぜカトリック教会は、今日見るような突然の変化をする必要があったのだろうか。
近代の三要因
近世の初頭に教会のあり方に大きく影響を与えた事柄が三つある。その第一は新大陸の発見である。アメリカ、アフリカ、インド等、世界の広がりと同時に、宣教熱も高まった。しかし教会が「輸出」したキリスト教は、原則としてヨーロッパ型のそれだった。こうして教会は真の世界の教会になる課題を今日にまで持ち越した。第二の要因は宗教改革である。その評価はともあれ、宗教改革は、教会分裂という新事実を生み、ローマ・カトリック教会は、七つの秘跡を中心とする教会観、教皇を頂点とする聖職位階制度、それらの存立を確実にする教会法の整備をもって、教会の制度的側面を強化していこうとした。
第三の要因は、近世の合理主義精神そのものである。合理主義精神は、自律の精神でもある。神さま抜きで、人間が自分で理解し、把握できることだけを信用しようとする姿勢である。これは主に、知識・学問と政治・社会の二つの次元で展開した。近代的学問は、一方で合理的根拠を疑われた聖書やキリスト教信仰への懐疑として現れ、他方では、今日の科学技術社会・消費社会の基盤を築いていった。社会面では、市民階級の台頭に始まり、絶対君主制度、市民革命を経て、国民国家の成立へと進んでいった。政教分離の名のもとに、社会は脱宗教的な色あいを徹底して深めていった。
教会はこのような展開の中で一般社会の動向と袂を分かつ方向へと進んでいった。世俗は人間の自然的生命のために力を尽くし、教会は超自然の生命を育むことに専念するという分業体制である。とくに十九世紀後半から二十世紀初頭にかけてこの傾向は強まった。近代文明が生んだ政治理論や思想の多くが近代主義として弾劾され、禁書目録が示され、近世合理主義を論駁する新スコラ学が教会の神学とされた。
「閉じられた教会」からの脱皮
近代的教会は、このようにして多くの現実に対して「閉じられた教会」となっていった。より広がった世界に対して、プロテスタント教会に対して、そして一般社会の動き全体に対して。人間の主要関心の領域は「世俗」として切り捨てられ、教会は超自然の世界に自己限定することによって、その存立を維持しようとした。これはある意味で成功した。冒頭で述べたような荘厳は教会の場を確立したからである。
しかしイエスの福音を受け継ぐ教会の使命は、このような社会との隔絶によって全うされる性質のものではない。とくに二十世紀に入ってからの一般社会の変化は加速度的であり、教会とのギャップは修復しがたいほどのものになりかけていた。教会は早急に世界の諸現実に対して開かれる必要があった。当時のカトリック教会が、その緊急性をどの程度意識していたかは別の話である。
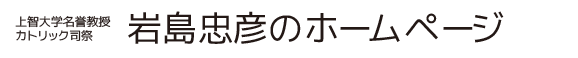

 第二ヴァティカン公会議で何が起...
第二ヴァティカン公会議で何が起...